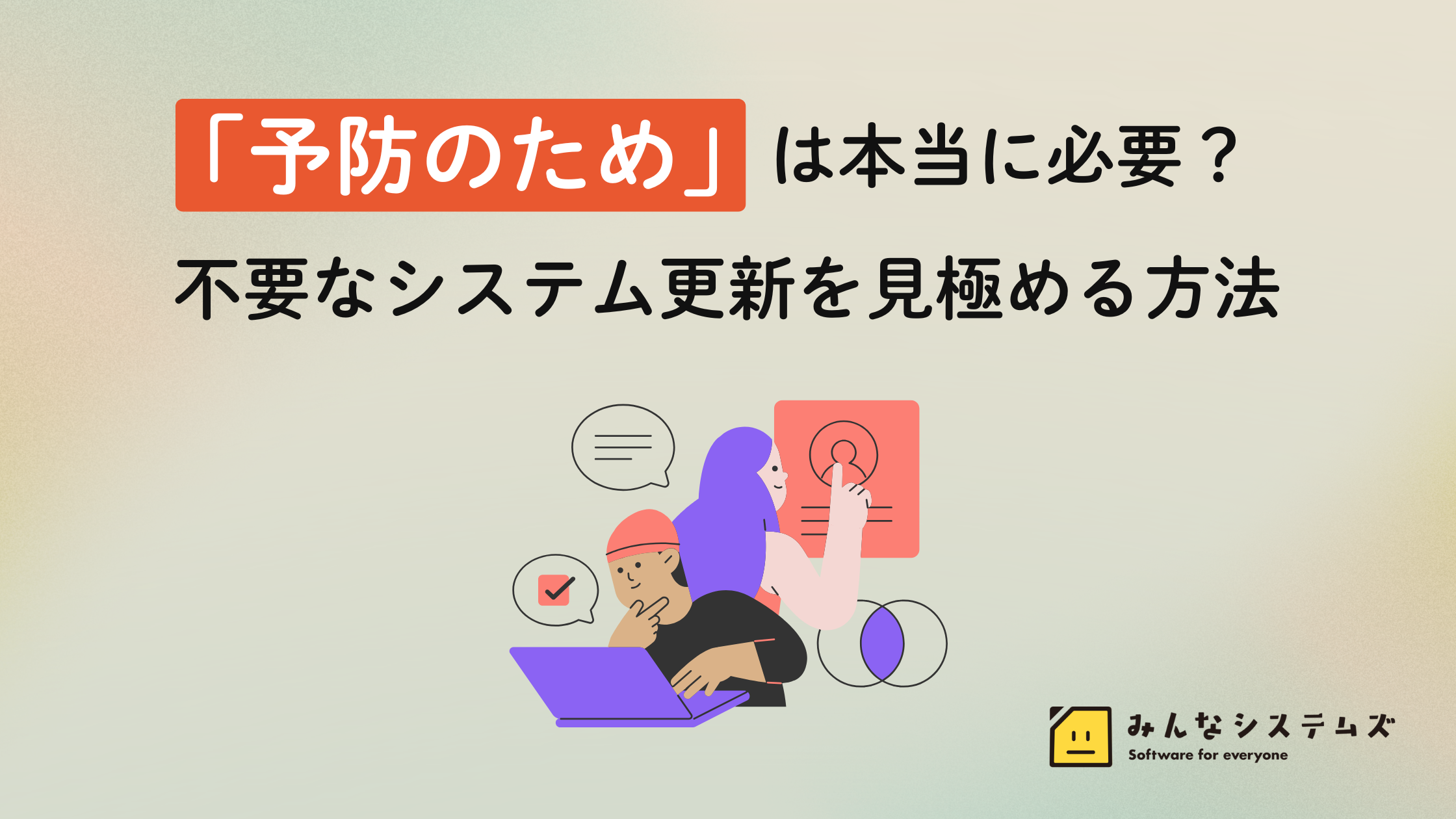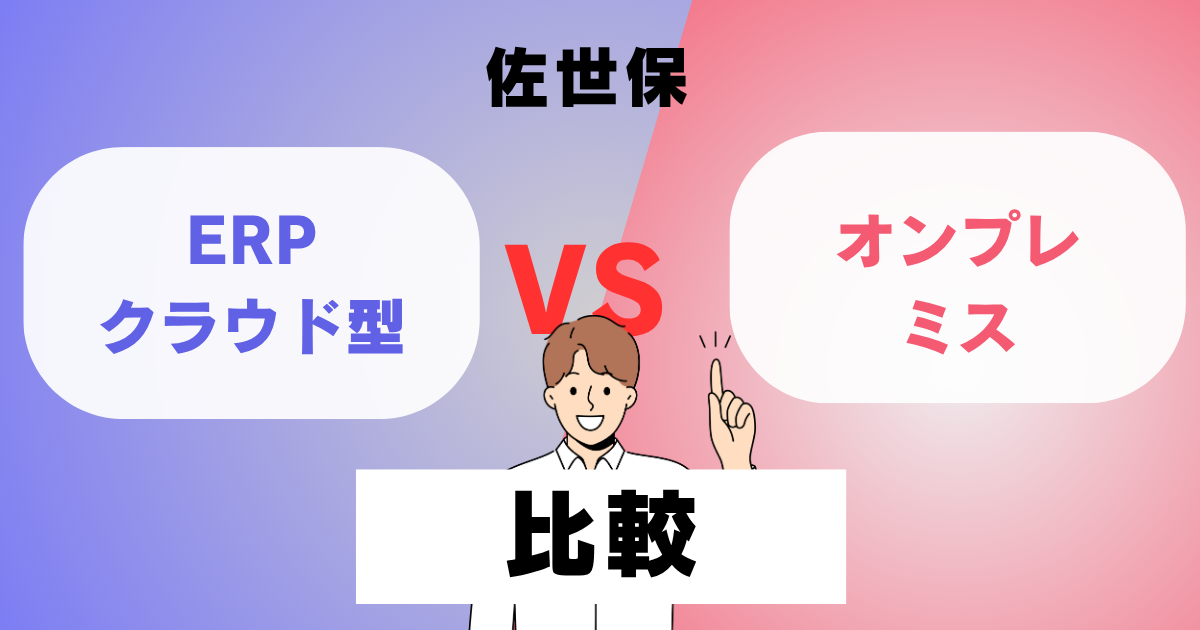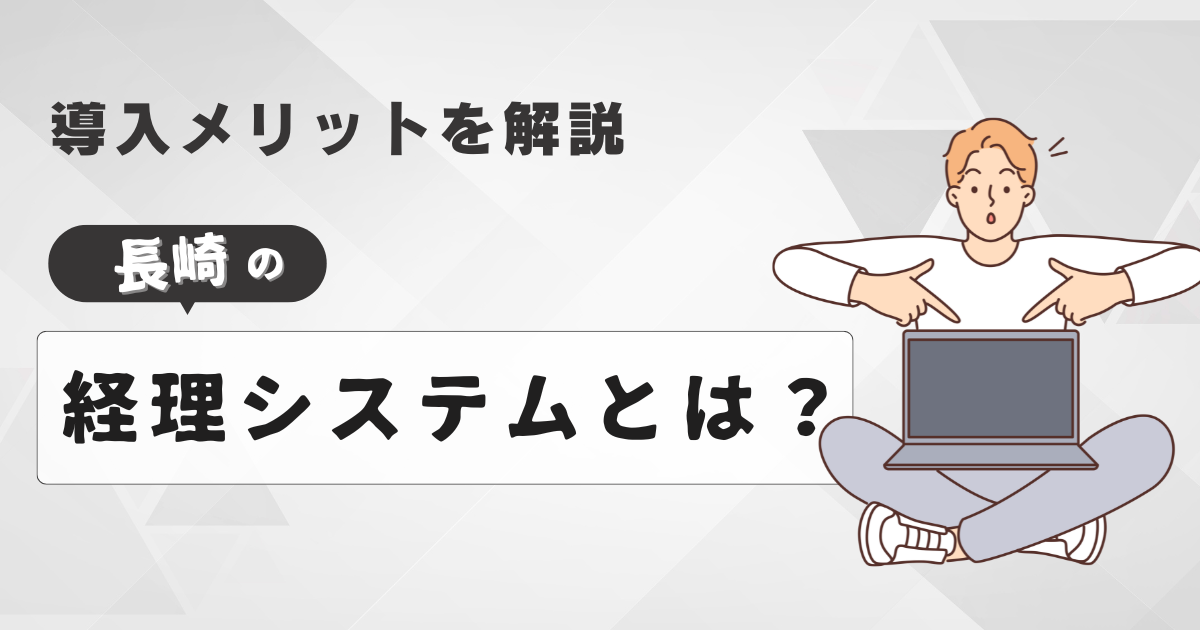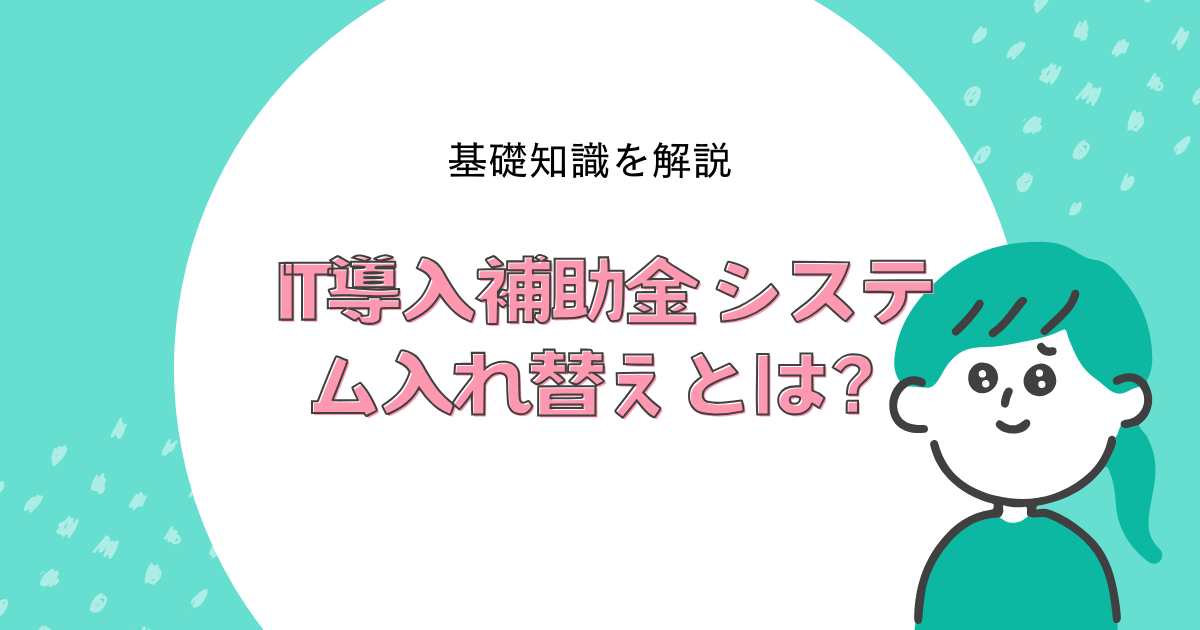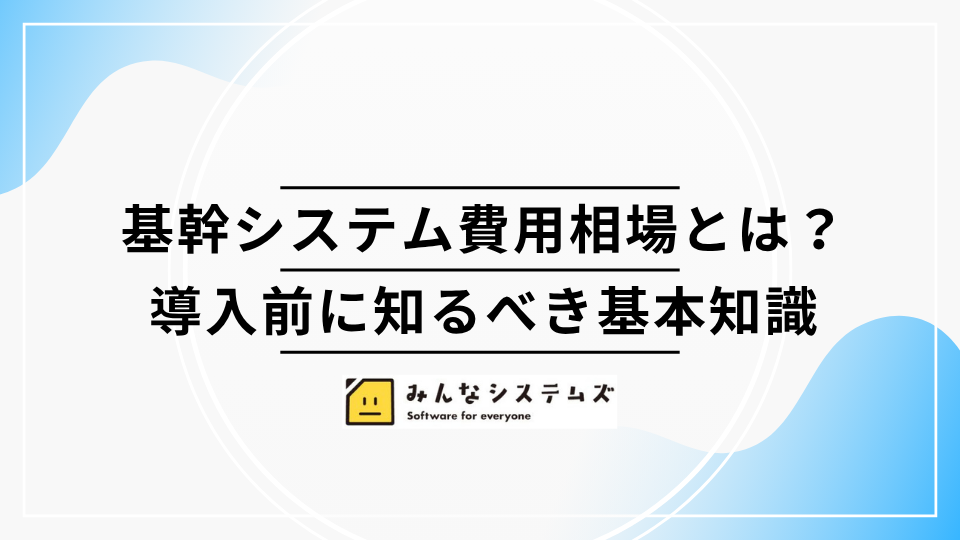「念のため」の更新提案、本当に必要ですか?
「Windows更新に備えて、予防的にシステム改修をしておきましょう。お見積もりは80万円です」
実際には何も問題が起きていないのに、こんな提案を受けた経験はありませんか?「予防のため」「将来のリスク回避のため」という言葉に押され、よく分からないまま承認してしまう…。
しかし、その更新は本当に必要なのでしょうか?本記事では、不必要なシステム更新を見極める方法と、ベンダーの提案を正しく判断するためのポイントを解説します。
なぜ「不必要な更新」が提案されるのか?
ベンダー側の収益構造
システム会社にとって、保守契約だけでは十分な収益が得られないケースが少なくありません。そこで:
- 定期的な改修案件を作り出すことで、安定収益を確保
- 「予防保全」という名目なら、顧客も断りにくい
- 実際に問題が起きなければ「改修のおかげ」と評価される
つまり、ベンダーにとって「予防的改修」は、リスクが低く収益性の高いビジネスモデルなのです。
「不安」を煽るセールストーク
よくある提案の例を見てみましょう:
パターン1:曖昧なリスク提示 「次のWindows更新で、御社のシステムに影響が出る『可能性』があります」 → 可能性はゼロではないが、実際の確率や影響範囲は示されない
パターン2:責任回避の予防線 「今対応しておかないと、もし問題が起きた時は緊急対応になり、さらに高額になります」 → 起きるか分からない未来のリスクで判断を迫る
パターン3:他社事例の一般化 「別のお客様で問題が発生しましたので、御社も対応をお勧めします」 → 他社のシステム構成と自社が同じとは限らない
こうした説明では、「本当に必要なのか」を判断する材料が不足しています。
技術的根拠の不透明さ
本当に必要な改修なら、以下が明確に説明できるはずです:
- どのWindows機能の変更が影響するのか
- システムのどの部分が影響を受けるのか
- 影響が発生する確率はどの程度なのか
- 対応しなかった場合の具体的な症状は何か
これらが曖昧なまま「とにかく予防が必要」と言われたら、黄色信号です。
過剰な安全マージン
もちろん、予防保全自体は悪いことではありません。しかし:
- 発生確率5%未満のリスクに80万円かけるのは妥当か?
- 影響があっても軽微で、事後対応で十分なケースではないか?
- 本当に今やるべきか、次回のシステム刷新まで先送りできないか?
費用対効果を考えず、「念のため全部やる」という姿勢は、結果的にIT投資の無駄遣いにつながります。
不必要な更新を見極める5つのチェックポイント
1. 具体的な技術的根拠があるか?
良い提案の例: 「Windows 11ではIE(Internet Explorer)が完全削除されます。御社の販売管理システムはIEに依存しているため、ブラウザをEdgeに対応させる改修が必要です」
悪い提案の例: 「Windows更新により、システムに何らかの影響が出る可能性があります。念のため、システム全体の検証と調整をお勧めします」
前者は影響範囲が明確ですが、後者は「何らかの」「可能性」という曖昧な言葉で具体性がありません。
2. 影響が発生する確率は示されているか?
- 「ほぼ確実に影響します」→ 対応すべき
- 「影響する可能性があります」→ 確率次第
- 「影響が出たお客様もいます」→ 自社への関連性を確認
確率が示されない場合は、「過去の同様のWindows更新で、同じ構成のシステムに何%の確率で問題が起きましたか?」と質問してみましょう。
3. 対応しなかった場合の最悪シナリオは?
- システムが完全に起動しなくなる → 対応必須
- 一部機能が使えなくなる → 代替手段や回避策を検討
- 動作が遅くなる可能性がある → 様子見も選択肢
リスクの重大性を正しく理解することで、優先順位をつけられます。
4. 事後対応との費用比較はされているか?
予防改修:80万円 vs 万が一問題が起きた場合の緊急対応:30万円(発生確率10%)
この場合、期待値は3万円。予防に80万円かけるのは過剰かもしれません。
ベンダーは「緊急対応はもっと高額」と言いがちですが、具体的な見積もりを求めましょう。
5. セカンドオピニオンを取れるか?
他のシステム会社やITコンサルタントに相談することで:
- 提案の妥当性を客観的に評価できる
- 別の解決策(より低コストな対応方法)が見つかる可能性
- ベンダーに対する交渉材料になる
「長年の付き合い」を理由に、一社の意見だけで判断するのは危険です。
賢い対応策:「見極める力」を持つ
段階的アプローチを提案させる
一度に全てを改修するのではなく:
ステップ1: まずは影響調査のみ実施(10万円) ステップ2: 問題が確認されたら、必要な部分だけ改修(30万円) ステップ3: 様子を見て、必要なら追加対応
このように段階的に進めることで、不要な支出を避けられます。
「やらない選択肢」も明示させる
見積もりを依頼する際、必ず以下も聞きましょう:
- 「対応しなかった場合、何が起きますか?」
- 「問題が起きる確率はどのくらいですか?」
- 「問題が起きたら、その時点で対応する費用はいくらですか?」
これらの情報があれば、合理的な判断ができます。
保守契約の範囲を明確にする
「予防的な検証」は保守範囲に含まれるべきです。毎回別料金なら、保守契約の意味がありません。
理想的な保守契約:
- Windows更新による影響調査は保守範囲内
- 実際に問題が発生した場合の対応も保守範囲内
- 予防的な大規模改修は別見積もり(ただし根拠を明示)
契約更新時に、この点を明確化しましょう。
クラウド移行で「予防改修」から解放される
根本的な解決策は、やはりOS依存から脱却することです。
クラウドERPなら:
- Windows更新の影響を受けない
- 「予防的改修」という概念自体が不要
- ベンダーが全て管理するため、追加費用も発生しない
初期投資は必要ですが、毎年の「念のため改修」から解放されるメリットは大きいです。
実際の見極め事例
製造業E社の場合(従業員35名)
ベンダーからの提案: 「Windows 11への対応として、システム全体の検証と調整を行いましょう。費用は120万円です」
E社の対応:
- 具体的な影響範囲を質問 → 「全体的に検証が必要」との回答(曖昧)
- セカンドオピニオンとして別のIT会社に相談
- 「影響があるのは帳票印刷部分のみ。対応費用は20万円程度」との評価
結果: セカンドオピニオンの会社に依頼し、100万円のコスト削減に成功。「なんとなく怖いから」で判断せず、専門家の意見を複数聞くことの重要性を実感。
小売業F社の場合(従業員20名)
ベンダーからの提案: 「予防的にデータベースサーバーをアップグレードしましょう。費用は60万円です」
F社の対応:
- 「なぜ今必要か?」を質問 → 「いずれ必要になるから」との回答
- 「現状で問題は?」→「特にないが、予防のため」
- システム刷新を1年後に控えていることを考慮
結果: 提案を保留し、1年後のシステム刷新時にクラウドERPへ移行。60万円の無駄遣いを回避し、かつ根本的な解決を実現。
まとめ:「予防」と「過剰」の線引きを
ベンダーからの「予防的改修」提案が全て不要というわけではありません。しかし、技術的根拠が不明確なまま、高額な費用を支払い続けるのは賢明ではありません。
今すぐ実践できること:
- 次回提案を受けた際、この記事の5つのチェックポイントで評価する
- 「やらない場合のリスク」を具体的に質問する
- 高額な提案には必ずセカンドオピニオンを取る
- 中長期的には、クラウド化などOS依存からの脱却を検討する
「念のため」という言葉に流されず、費用対効果を冷静に判断する。それだけで、年間数十万円から数百万円のIT投資を最適化できます。
あなたの会社のシステムに、本当に必要な投資は何か?まずは現状を客観的に診断することから始めませんか?
お問い合わせは今すぐ! 「この改修提案は妥当?」そんな疑問に、第三者の立場から客観的にお答えします。セカンドオピニオンサービスで、適切なIT投資判断をサポートいたします。