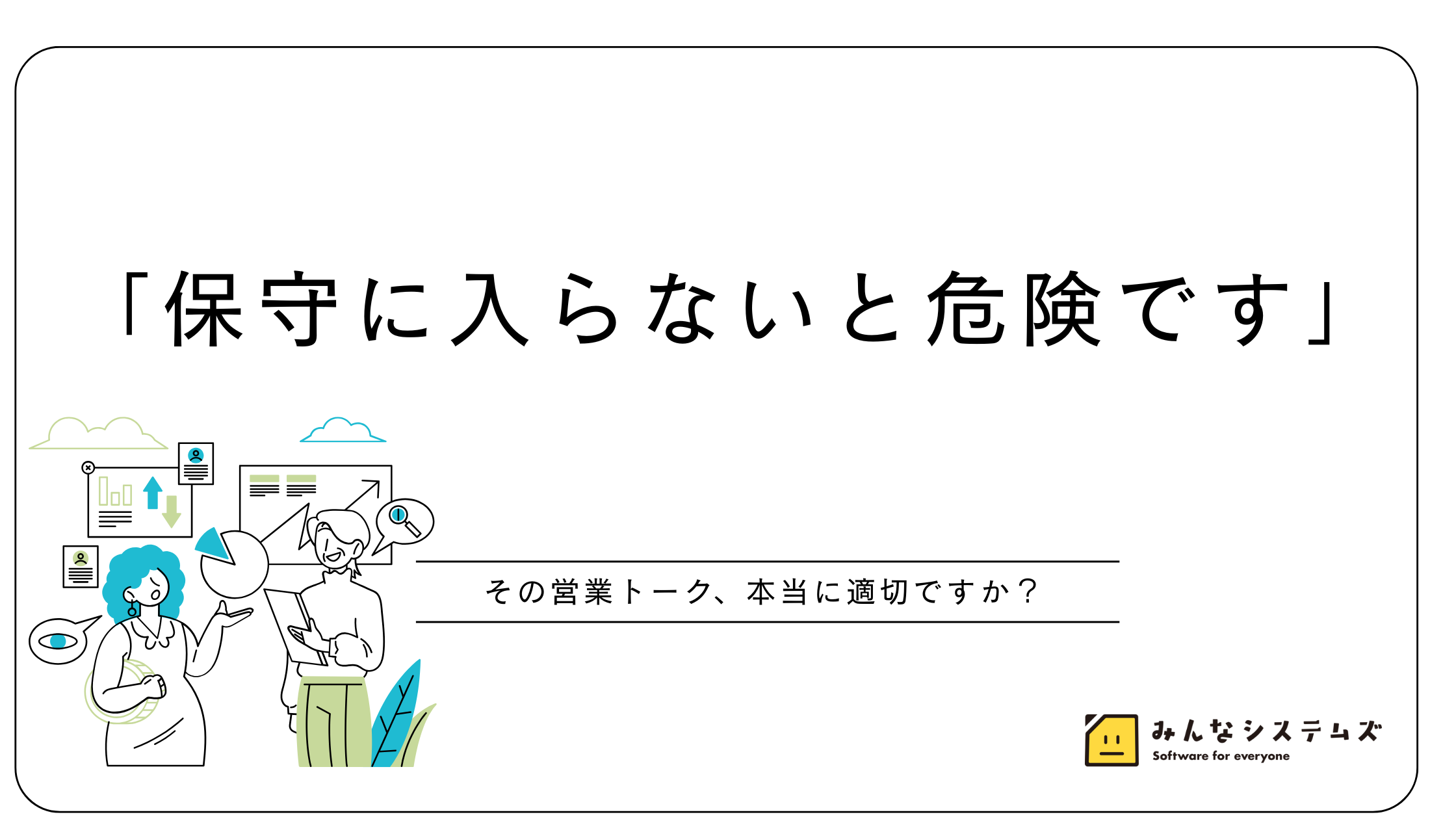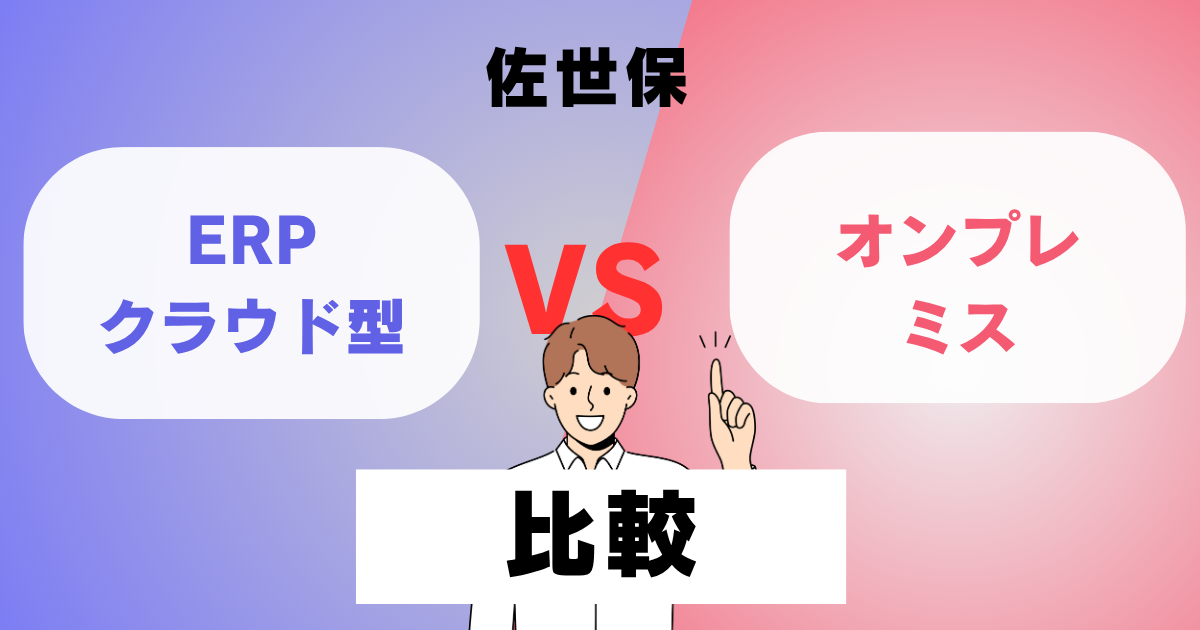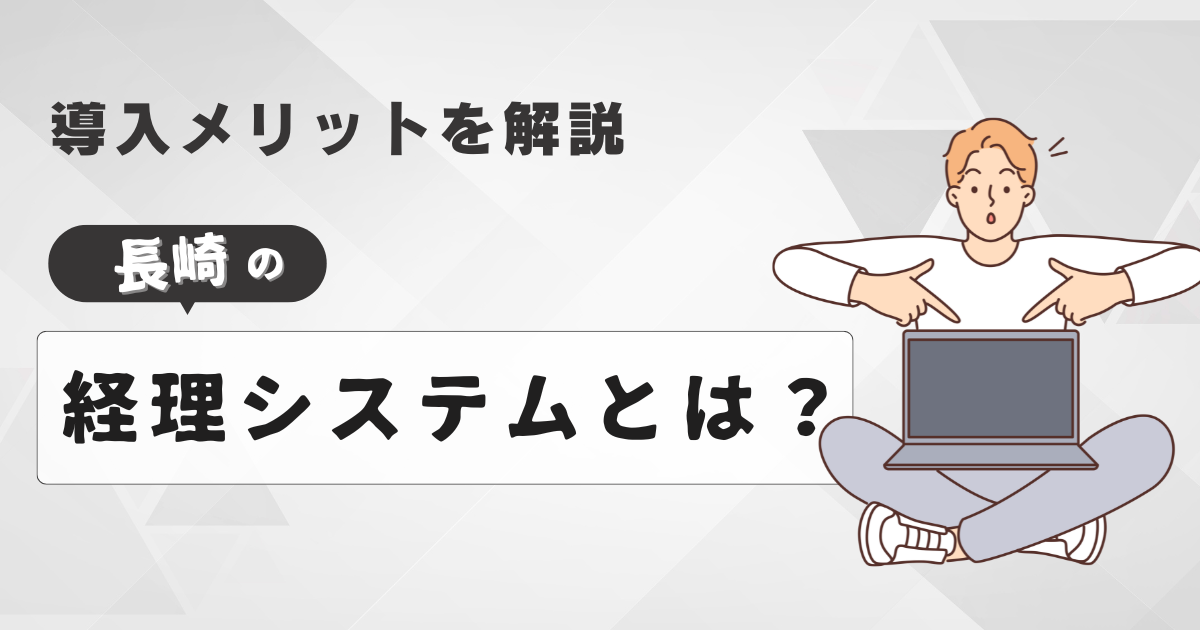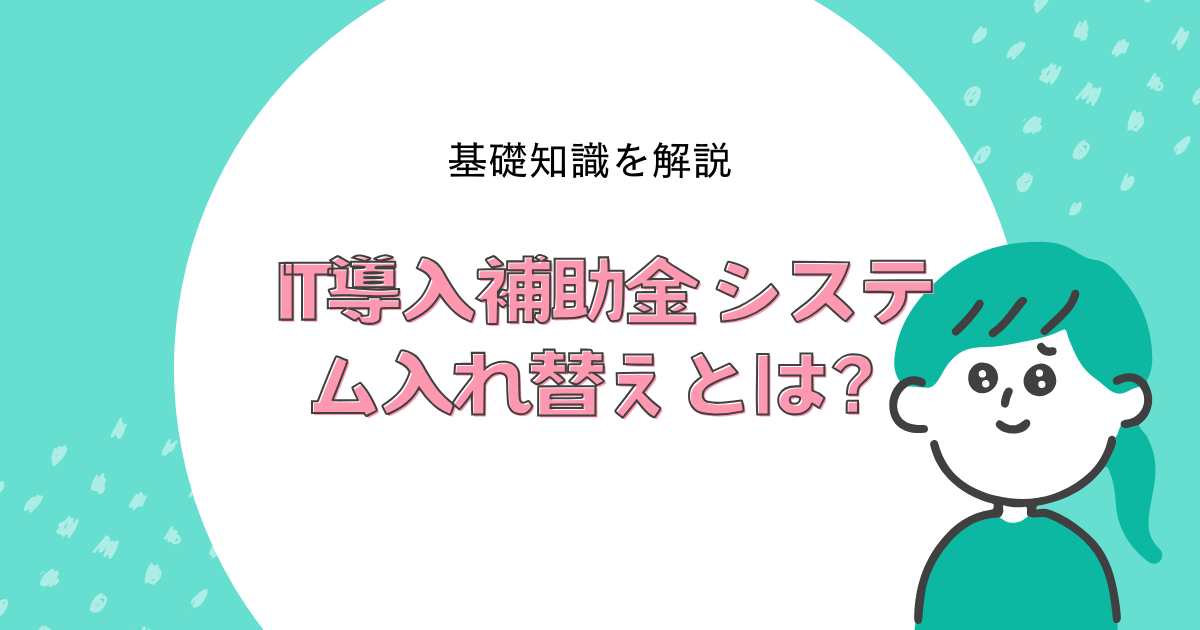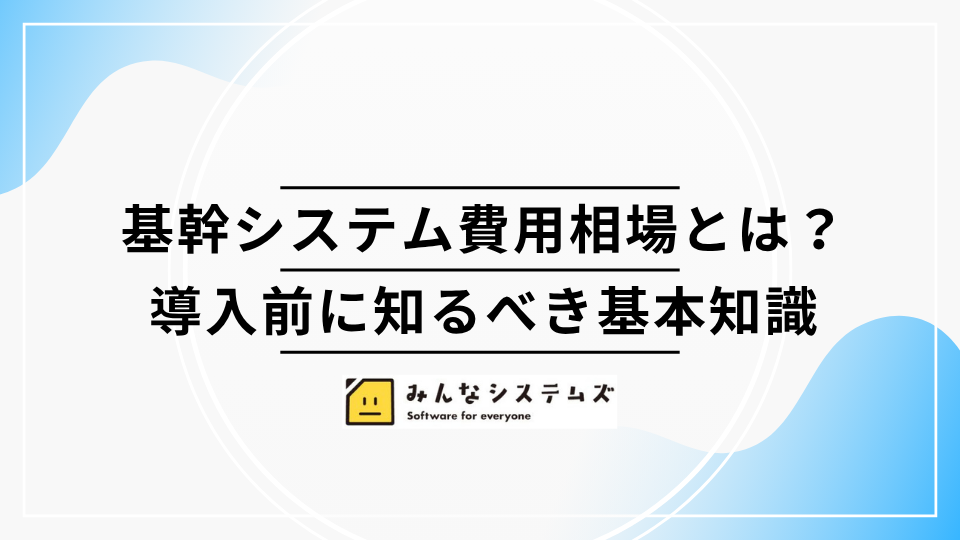システム保守の"脅し営業"に悩んでいませんか?
「保守契約に加入しないと、システムトラブル時に数百万円の費用がかかりますよ」 「サポートなしで使い続けると、いつ止まってもおかしくないですよ」
こうした言葉で不安を煽られ、高額な保守契約を結ばされた経験はありませんか?
実は、中小企業の多くが、ベンダー(システム開発会社)からの脅迫的な保守営業に悩まされています。本来、保守契約は企業の安心を支えるためのものであるはずが、いつの間にか「入らざるを得ない」強制的なものになっているケースが少なくありません。
今回は、この「脅迫的な保守営業」の実態と、そこから抜け出すための具体的な方法について解説します。
なぜ「脅迫的な保守営業」が横行するのか?
保守契約とは何か
まず基本的な知識として、保守契約について整理しましょう。保守契約とは、システムの運用中に発生するトラブル対応やバージョンアップ、問い合わせ対応などを提供するサービスです。
一般的には以下のような内容が含まれます:
- システムの不具合修正
- 問い合わせ対応(電話・メール)
- 法改正や環境変化への対応
- セキュリティパッチの適用
- バックアップや監視サービス
これらは確かに重要なサービスですが、問題はその提供方法と価格設定にあります。
不安を煽る営業手法の実態
多くの中小企業が経験している脅迫的な保守営業には、次のような特徴があります:
1. 極端なリスクの強調 「保守に入らないと、システムが止まった時に会社が潰れますよ」といった極端な表現で不安を煽ります。確かにシステムトラブルは深刻ですが、適切なリスク管理の説明ではなく、感情的な不安を掻き立てる手法です。
2. 選択肢を与えない契約形態 「保守契約なしでは一切サポートしません」「スポット対応は通常の5倍の料金です」といった、実質的に保守契約を強制する仕組みです。
3. 不透明な保守費用 「何が含まれているのか」が不明瞭なまま、システム導入費用の15〜20%といった高額な年間保守費用を請求されるケースもあります。
4. 解約時の脅し文句 「保守を解約すると、今後一切対応できません」「他社に移行しても、うちのシステムは複雑すぎて誰も触れませんよ」といった言葉で、解約を阻止しようとします。
なぜこうした営業が成立してしまうのか
この背景には、以下のような構造的な問題があります:
- 情報の非対称性: IT知識が乏しい企業は、ベンダーの言うことを信じるしかない
- ベンダーロックイン: 特定のベンダーに依存する状態(ベンダーロックイン)になると、他社への切り替えが困難
- 属人化: システムを構築した担当者しか分からない状態になっている
- 契約時の力関係: システム導入時に保守契約とセットで契約させられる
脅迫的な保守営業から抜け出すための5つのステップ
では、こうした状況から抜け出すにはどうすればよいのでしょうか。
ステップ1:現状の保守契約を見直す
まずは、現在の保守契約の内容を詳しく確認しましょう:
- 保守費用は年間いくらか?
- その費用で何が提供されているのか?
- 過去1年間で実際にどれだけ保守サービスを利用したか?
- 契約書に不利な条項(高額な解約金、自動更新など)はないか?
多くの場合、「ほとんど使っていないのに高額な保守費用を払い続けている」という実態が見えてきます。
ステップ2:他社の見積もりを取る
現在のベンダーから「他社では対応できない」と言われても、それが真実とは限りません。複数の他社ベンダーに相談し、以下を確認しましょう:
- 既存システムの保守・運用が可能か
- 保守費用はどの程度か
- システムの移行が可能か、その費用はいくらか
重要なポイント: 見積もりを取ること自体が、現在のベンダーとの価格交渉の材料にもなります。
ステップ3:段階的な脱却計画を立てる
いきなり完全に縁を切るのではなく、段階的に依存度を下げる計画を立てましょう:
- 短期(3〜6ヶ月): 保守契約の内容を精査し、不要なサービスを削減
- 中期(6ヶ月〜1年): 他社へのセカンドオピニオンを得る、または並行して新システムの検討開始
- 長期(1〜2年): 新システムへの移行、または複数ベンダーでの保守体制構築
ステップ4:社内のIT体制を強化する
外部依存を減らすため、社内のIT理解度を高めることも重要です:
- システムのドキュメント(仕様書・操作手順書)を整備する
- 簡単なトラブル対応は社内でできるようにする
- IT担当者を育成する、または採用する
完全に内製化する必要はありませんが、「ベンダーに言われるがまま」の状態から脱却することが大切です。
ステップ5:適切な関係性を構築する
最終的には、脅迫や依存ではなく、対等なパートナーシップを築けるベンダーを選ぶことが重要です。
良いベンダーの特徴:
- リスクを正直に、かつ冷静に説明する
- 複数の選択肢を提示してくれる
- 保守契約の内容が明確で透明性が高い
- 解約時にも誠実に対応する
実際に保守営業から抜け出した企業の事例
事例1:製造業A社(従業員50名)の場合
状況: 15年前に導入した販売管理システムの保守費用が年間200万円。ほとんどサポートを利用していないのに、「保守がないと法改正対応ができない」と言われ続けていた。
アクション:
- 他社ベンダー3社に相談し、既存システムの保守が年間80万円で可能と判明
- 現ベンダーに他社見積もりを提示し、価格交渉を試みるも拒否される
- 1年かけて新しいクラウドERPに移行を決断
- 新システムでは保守費用が年間60万円、機能も向上
結果: 年間140万円のコスト削減に成功。「もっと早く動けばよかった」と経営者は語っています。
事例2:卸売業B社(従業員30名)の場合
状況: 在庫管理システムのベンダーから「保守を解約するとデータが消える可能性がある」と脅され、年間150万円の保守契約を10年間継続。
アクション:
- 別のIT企業に相談し、データバックアップの方法を学ぶ
- 実際には保守契約とデータ保持は無関係であることが判明
- 段階的に保守範囲を縮小し、スポット契約に変更
- 最終的には保守費用を年間50万円まで削減
結果: 10年間で合計1000万円以上も余分に支払っていたことが判明。現在は必要な時だけサポートを依頼する体制に。
まとめ:不安に支配されず、適切な判断を
「保守に入らないと危険」という言葉は、必ずしも嘘ではありません。確かにシステムの保守は重要です。しかし、それを不安を煽る道具として使うのは、健全なビジネス関係とは言えません。
重要なのは以下の3点です:
- 現状を正しく把握すること: 保守契約の内容と実際の利用状況を確認する
- 選択肢を知ること: 他社の意見を聞き、複数の選択肢を比較する
- 段階的に行動すること: 焦らず、計画的に依存状態から脱却する
脅迫的な保守営業は、あなたの会社の成長を阻害する足枷になっています。不安に支配されるのではなく、正しい情報に基づいて適切な判断をすることで、健全なIT環境を構築できます。
「おかしいな」と感じたら、それは正しい直感かもしれません。まずは現状の保守契約を見直すことから始めてみませんか?
この記事に関するご相談、または既存システムの保守についてのセカンドオピニオンをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。中小企業の皆様が適切なIT環境を構築できるよう、誠実にサポートいたします。