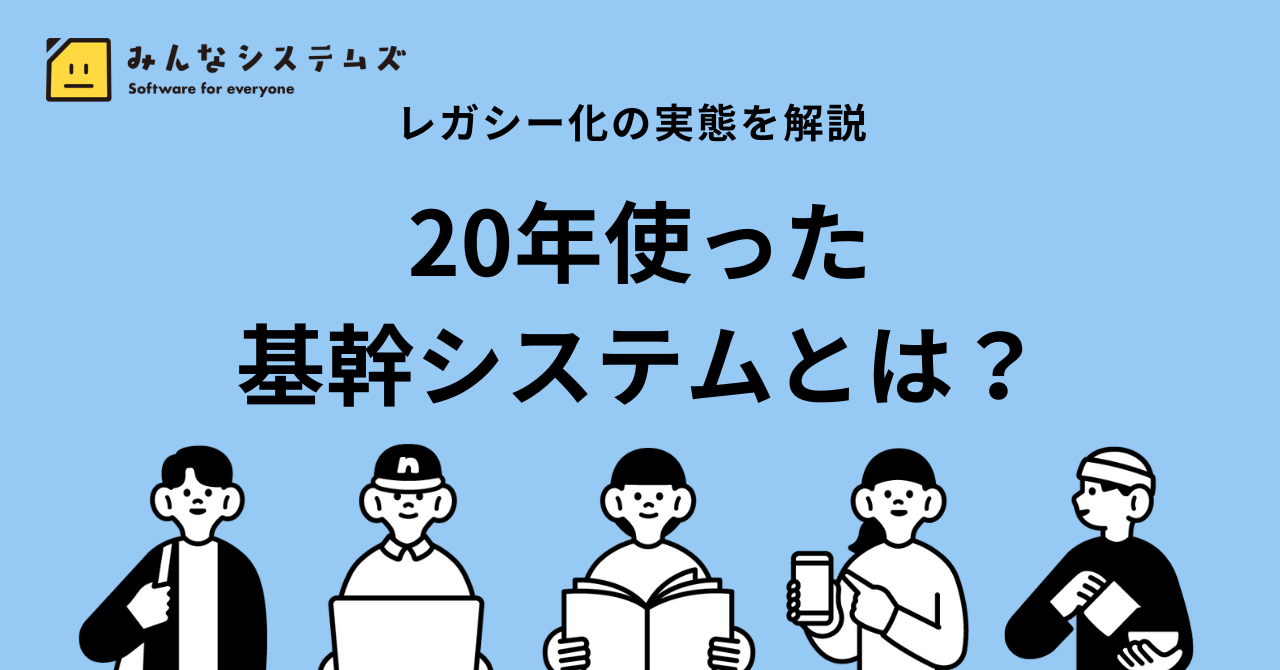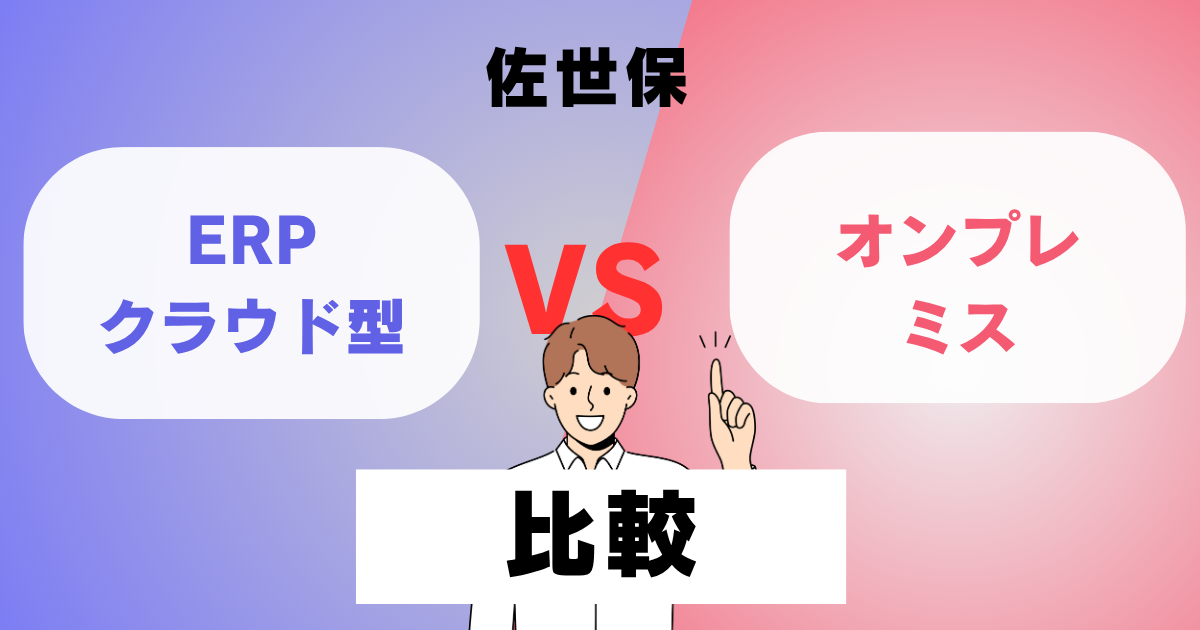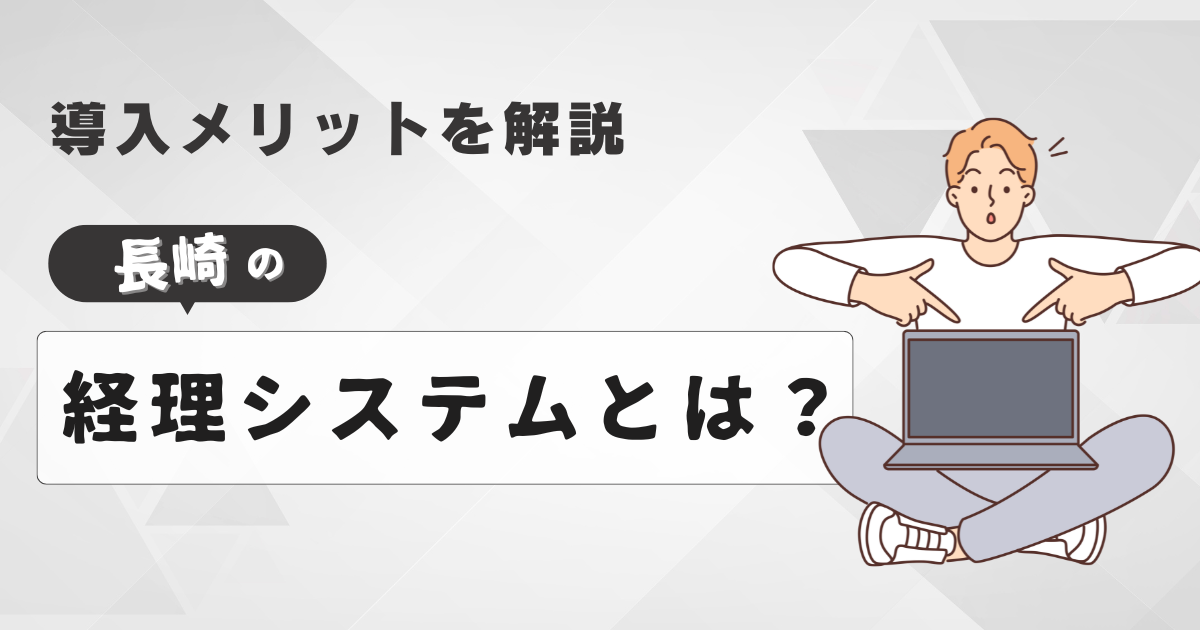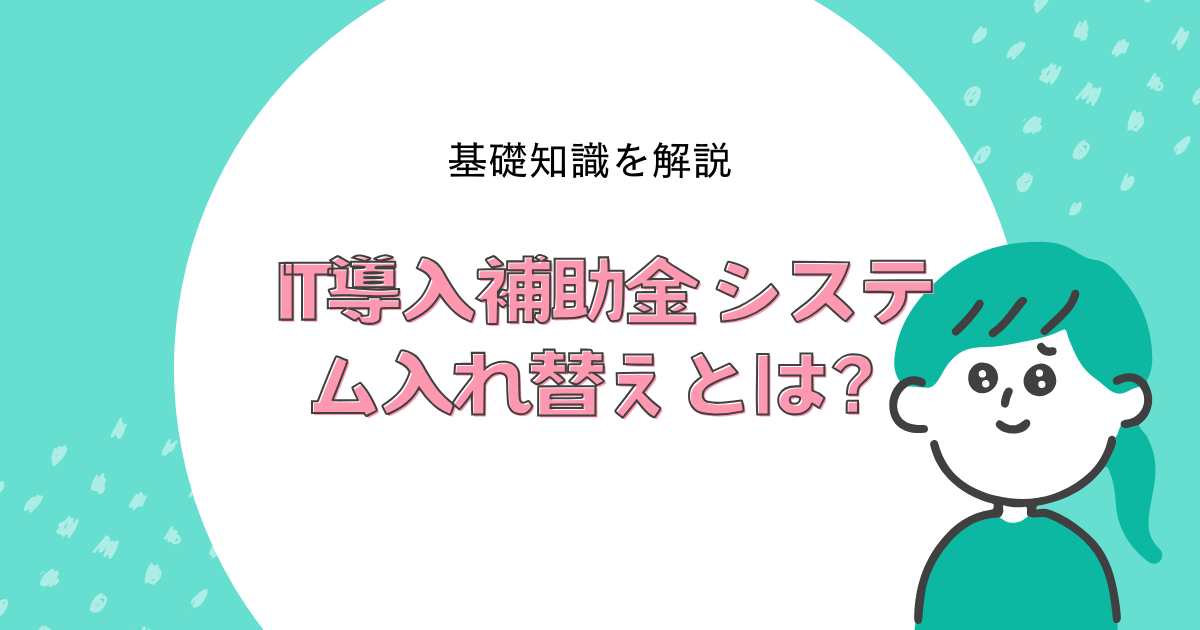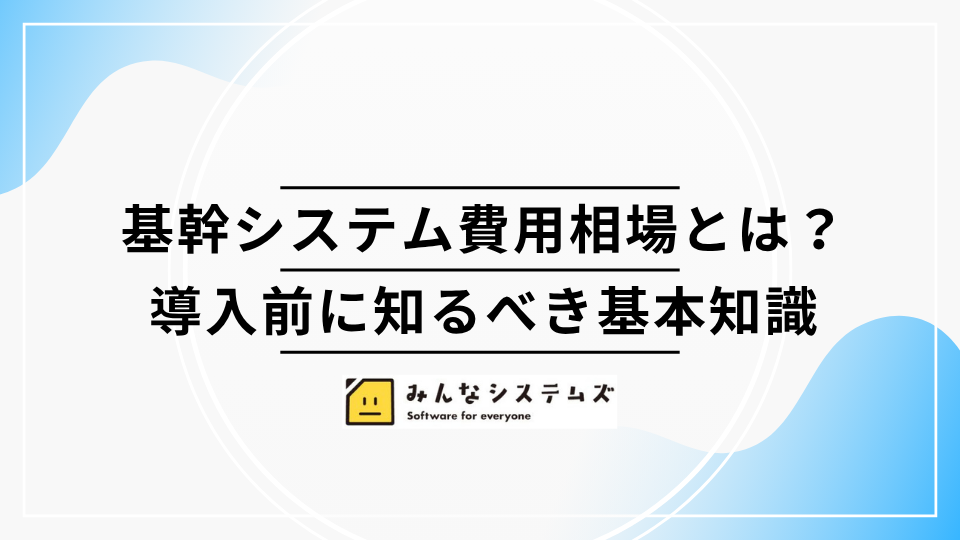みなさんこんにちは、株式会社みんなシステムズの営業の岩永です。
今回は、先日長崎県佐世保市のお客様で経験した、まさに「20年モノ」の基幹システムリプレイス作業についてお話しさせていただこうと思います。システムが古いと言っても、実際どんな問題があるのか、ピンとこない方も多いのではないでしょうか。現場で見てきた生々しい実態を交えながら、わかりやすく解説していきますね。
20年使った基幹システムの現状とは
20年使った基幹システムは、多くの企業で深刻な課題となっています。経済産業省の調査によると、日本企業の約6割が15年以上前に構築されたシステムを継続使用しており、技術的負債が蓄積されている状況です。これらのシステムは当初の設計思想から大きく乖離し、現代のビジネス要求に対応できない状態となっています。
佐世保市のお客様の場合、1995年に導入したシステムをずっと使い続けていらっしゃいました。当時は最新鋭だったそのシステムも、今となってはまさに「化石」状態。でも、なぜ20年も使い続けることになったのでしょうか?
実は、理由は意外とシンプルなんです。「動いているから」「変更するのが怖い」「コストがかかりそう」という3つの理由で、つい現状維持を続けてしまうんですね。まるで古い車を「まだ動くから」と言って乗り続けているような感覚です。
レガシー化が進む基幹システムの特徴
技術的な課題
長期間使用されたシステムでは、古いプログラミング言語やデータベースが使用されており、保守性の低下が顕著です。COBOLやFORTRANなどの古い言語で構築されたシステムでは、対応できるエンジニアの確保が困難になっています。
佐世保市のお客様のシステムも、Visual Basic 6.0という今では「絶滅危惧種」とも言えるプログラミング言語で作られていました。システムに詳しい社員の方がおっしゃっていたのは「もうVB6を知っている若いエンジニアはいません。私たちが引退したら、誰がこのシステムを保守するんでしょうか...」という切実な声でした。
実際に、過去5年間でシステムの改修を依頼できる会社を探すのに苦労されたそうです。見積もりを依頼しても「古すぎて対応できません」と断られることが多く、対応してくれる会社があっても非常に高額な見積もりになってしまうという悪循環に陥っていました。
運用面での問題点
システムの複雑化により、変更コストが高額になる傾向があります。小さな機能追加でも大規模な改修が必要となり、開発期間も長期化します。また、システム全体の動作を完全に把握している担当者が限られるため、属人化のリスクも高まります。
「消費税率の変更対応だけで200万円かかった」というお話を聞いた時は、本当に驚きました。現代的なシステムなら設定変更だけで済むような作業が、古いシステムでは大がかりな改修作業になってしまうんです。
さらに困ったことに、このシステムの詳細を知っているのが、社内でたった1人の方だけという状況でした。その方が体調を崩されて入院された時は、会社全体が大混乱に陥ったそうです。まさに「キーマンリスク」の典型例ですね。
長期利用による業務への影響
生産性の低下
20年使った基幹システムでは、処理速度の低下や操作性の悪化により、業務効率が大幅に低下します。手作業での対応が増え、従業員の作業負荷が増大する結果となります。
データ入力作業を実際に拝見させていただいた時のことですが、一つの受注データを入力するのに15分もかかっていました。画面の切り替えが遅く、データを入力しても反映されるまでに10秒以上待たなければならない状態でした。
営業の方々にとって特に深刻だったのは、在庫確認の問題です。これまでは、お客様から在庫の問い合わせがあっても「会社に戻って確認してからご連絡します」と言うしかありませんでした。現場からシステムにアクセスする手段がなかったからです。
実際の改善例: システムリプレイス後は、営業の皆さんがタブレットから直接在庫情報を確認できるようになりました。お客様の目の前で「現在○個在庫があります」とその場で回答できるようになったことで、営業成約率が20%向上したそうです。
セキュリティリスク
古いシステムでは最新のセキュリティ対策が適用できず、サイバー攻撃のリスクが高まります。特にサポートが終了したOSやミドルウェアを使用している場合、脆弱性の修正が困難になります。
佐世保市のお客様のシステムは、Windows XPという今では完全にサポートが終了したOSで動いていました。「ウイルス対策ソフトも最新版がインストールできない状態で、毎日ドキドキしながら使っています」という担当者の方の言葉が印象的でした。
実際に、過去に一度マルウェアに感染してしまい、システムが3日間使えなくなったことがあったそうです。その間は全て手作業で対応せざるを得なく、残業時間が急増したという苦い経験もおありでした。
システム刷新を検討すべきタイミング
判断基準となる指標
以下の状況が複数該当する場合、刷新を検討すべきです:
- 年間保守費用がシステム構築費の15%を超える
- 新機能開発に6ヶ月以上を要する
- システム障害の復旧時間が長期化している
佐世保市のお客様の場合、これらの条件がすべて当てはまっていました。特に印象的だったのは、年間の保守費用が当初のシステム構築費用の30%にも達していたことです。「新しいシステムを作った方が安いんじゃないか」と冗談交じりにおっしゃっていましたが、実際その通りでした。
また、「月末処理」という定期作業が、以前は1日で終わっていたのに、データ量が増えるにつれて3日もかかるようになっていました。システムの処理能力の限界が明らかでした。
隠れたコストの存在
古いシステムを使い続けることで発生する「隠れたコスト」も見逃せません。例えば:
・作業効率の低下による人件費の増加 ・システム障害時の機会損失 ・セキュリティインシデントのリスク ・従業員のストレス増加による離職率の上昇
佐世保市のお客様では、システムの不具合でお客様をお待たせしてしまい、大口の契約を失ったことがありました。その損失額を考えると、新システムの導入費用なんて安いものだと気づかれたそうです。
モダナイゼーションの選択肢
段階的な移行アプローチ
リフト&シフトによる段階的移行が効果的です。重要度の低い機能から順次クラウド環境へ移行し、リスクを最小化しながら近代化を進められます。
佐世保市のお客様の場合も、いきなり全システムを入れ替えるのではなく、まず在庫管理システムから着手しました。この部分は比較的独立性が高く、万が一問題が発生しても事業への影響を最小限に抑えられるからです。
最初の3ヶ月で在庫管理システムが安定稼働することを確認してから、次の段階として受注管理システムに着手しました。このような段階的なアプローチにより、現場の方々も無理なく新しいシステムに慣れることができました。
クラウド化のメリット
新しいシステムをクラウド環境に構築することで、多くの問題が解決されました:
・サーバーの保守管理が不要になり、管理負担が大幅に軽減 ・自動バックアップにより、データ消失のリスクが解消 ・外出先からもアクセス可能になり、営業効率が向上 ・セキュリティ対策がクラウド事業者によって自動的に更新
UIの改善による劇的な効果
新システムでは、UIの改善に特に力を入れました。これまでのシステムは、画面が小さく、文字も読みにくく、操作方法も直感的ではありませんでした。
新システムでは、タッチパネル対応の大きな画面で、必要な情報が一目で分かるようにデザインしました。データ入力も、これまで15分かかっていた作業が5分で完了するようになりました。実に3倍の効率化です。
特に年配の従業員の方々からは「こんなに使いやすいなら、もっと早く変えてほしかった」という声をいただきました。文字が大きく表示されるようになったことで、目の負担も軽減されたそうです。
成功事例から学ぶポイント
製造業A社では、20年使用した基幹システムを3年計画で刷新し、業務効率を40%向上させました。重要なポイントは、現行業務の詳細分析と段階的な移行計画の策定でした。
佐世保市のお客様での成功要因を振り返ると、以下のようなポイントが挙げられます:
まず、現場の声を徹底的に聞いたことです。実際にシステムを使う方々の不満や要望を丁寧にヒアリングし、それを新システムの要件に反映させました。「こんな機能があったらいいな」という声を大切にしたんです。
次に、十分な検証期間を設けたことです。新旧システムを並行稼働させる期間を2ヶ月設け、問題がないことを確認してから完全移行しました。この間は手間が2倍になりましたが、安全性を最優先に考えた結果です。
そして、従業員教育に時間をかけたことです。新システムの操作方法について、全従業員を対象とした研修を実施し、一人ひとりが自信を持って使えるようになるまでサポートしました。
投資対効果の実際
システムリプレイスには確かに大きな投資が必要です。しかし、佐世保市のお客様の場合、投資対効果は期待以上でした。
導入から1年後の効果測定では: ・データ入力時間が67%短縮(15分→5分) ・月末処理時間が75%短縮(3日→0.75日) ・営業成約率が20%向上 ・システム障害によるダウンタイムがゼロに ・年間保守費用が50%削減
これらの効果により、投資回収期間は当初予定の5年から3年に短縮される見込みです。
移行時の注意点とリスク管理
もちろん、システム移行には様々なリスクが伴います。佐世保市のお客様の場合も、いくつかの課題に直面しました。
最も大変だったのは、20年分の過去データの移行作業です。古いシステムのデータ形式が特殊で、そのまま新システムに移すことができませんでした。データクレンジング作業に予想以上の時間がかかり、移行スケジュールが1ヶ月遅れることになりました。
また、長年慣れ親しんだシステムから新しいシステムへの切り替えに対する心理的な抵抗もありました。「前のシステムの方が良かった」という声も最初の頃はありました。しかし、丁寧なサポートを続けることで、最終的には全員に納得していただけました。
まとめ:20年使った基幹システムの見直しが重要
20年使った基幹システムの課題は、放置すれば企業競争力の低下に直結します。技術的負債の解消と業務効率化のため、計画的なシステム刷新への取り組みが不可欠です。
佐世保市のお客様での経験を通じて、レガシーシステムの問題がいかに深刻かを改めて実感しました。でも同時に、適切な計画と実行によって、これらの問題は確実に解決できることも分かりました。
「システムが古いのは分かっているけど、変更するのが不安」という気持ち、よく分かります。でも、現状維持にもリスクがあることを忘れてはいけません。競合他社が効率的なシステムを導入している中、古いシステムを使い続けることは、競争力の低下につながります。
もし現在、古い基幹システムの限界を感じていらっしゃるなら、まずは現状の課題を整理することから始めてみてください。私たち株式会社みんなシステムズでも、そのようなお客様のお手伝いをさせていただいております。20年モノのレガシーシステムでお困りの方は、お気軽にご相談ください。きっと、業務効率化への道筋が見えてくると思います。
システムリプレイスは確かに大きな決断です。でも、適切なパートナーと一緒に取り組めば、必ず成功させることができます。佐世保市のお客様のように、「もっと早くやっておけば良かった」と言っていただけるような結果を出せるよう、私たちも全力でサポートいたします。