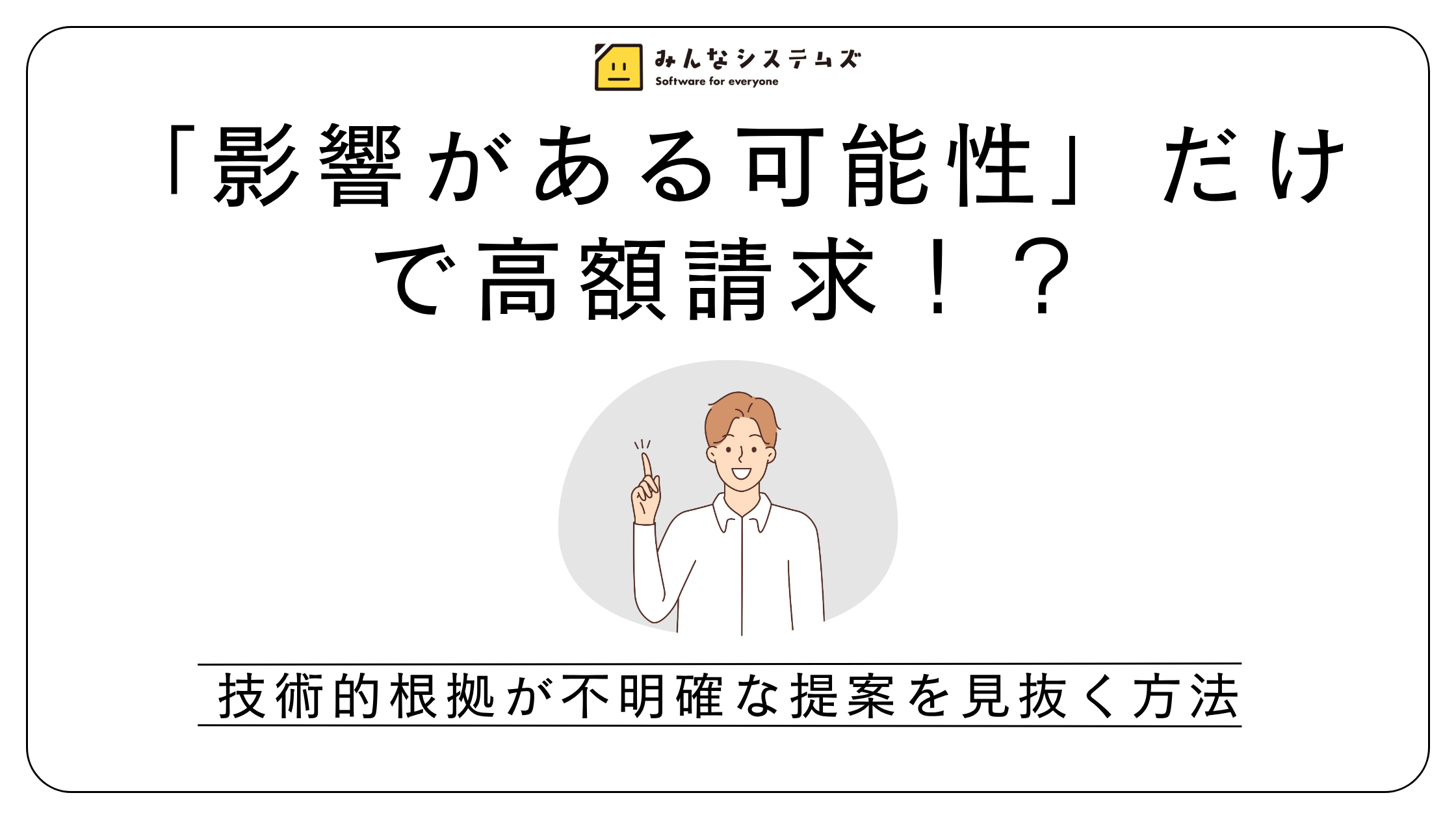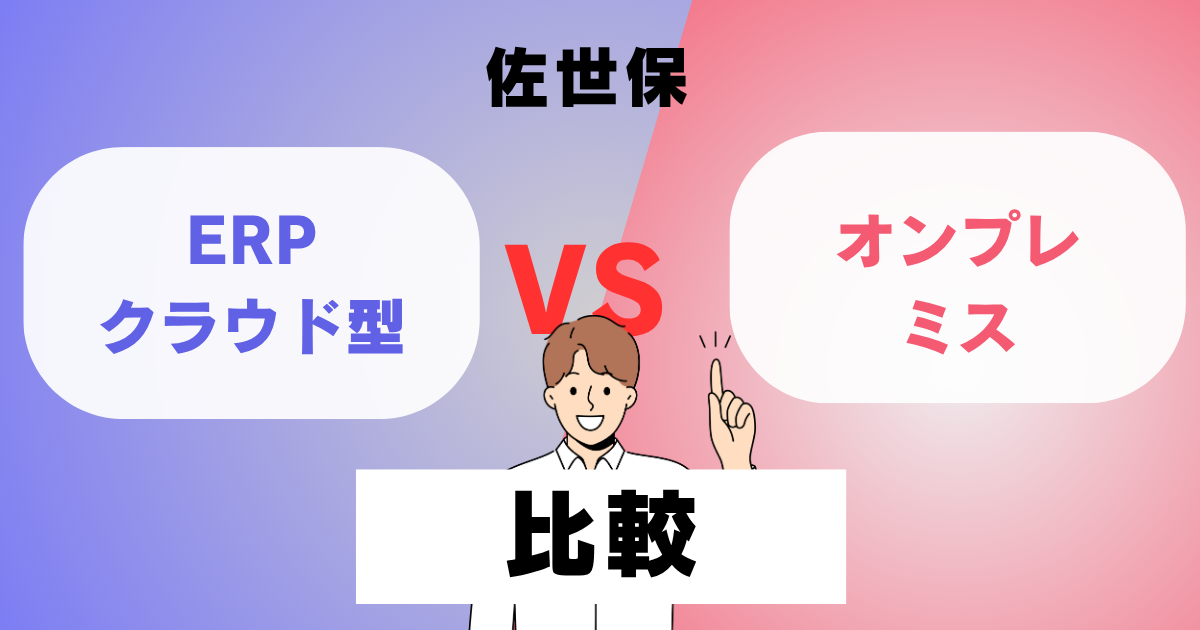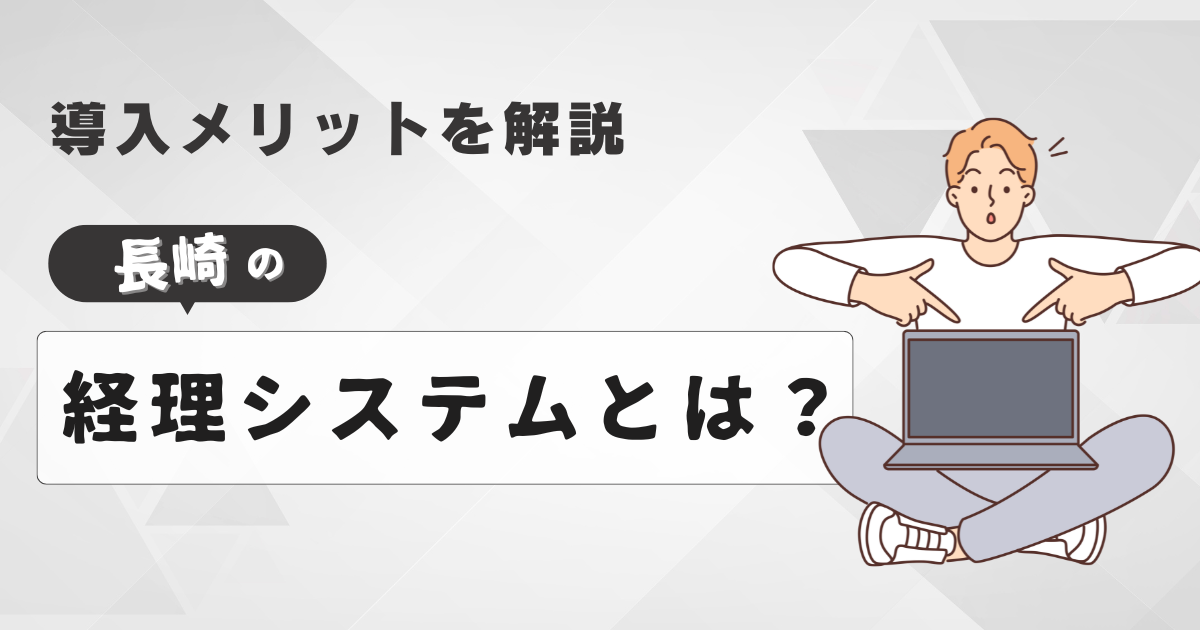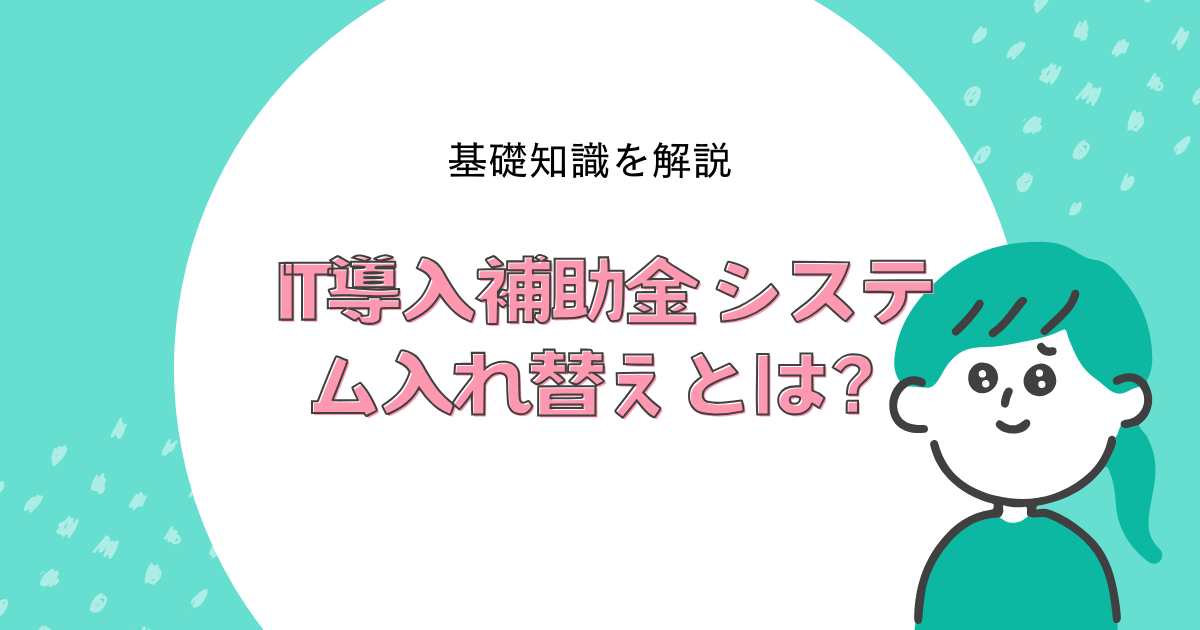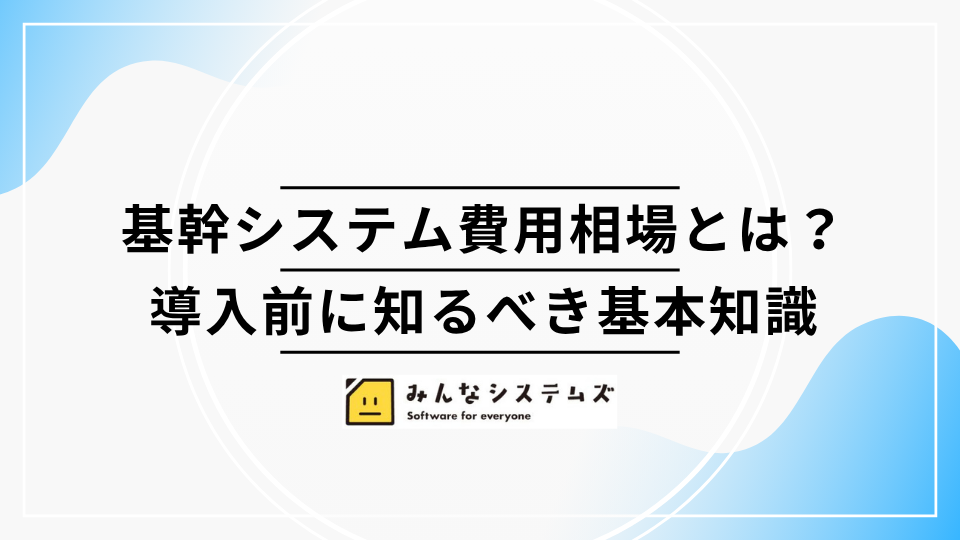「とにかく影響があります」で納得できますか?
「Windows更新により、御社のシステムに影響が出る可能性があります。対応が必要です。費用は150万円になります」
こんな説明を受けて、すぐに納得できるでしょうか?「何がどう影響するのか?」「なぜ150万円もかかるのか?」そう疑問に思いながらも、専門用語を並べられて反論できず、結局は承認してしまう…。
本記事では、技術的根拠が不明確な提案を見抜く方法と、ベンダーに適切な説明を求めるための具体的な質問例を解説します。
なぜ曖昧な説明が横行するのか?
「専門知識の非対称性」を利用した戦略
ベンダーとクライアントの間には、圧倒的な技術知識の差があります。この差を利用すれば:
- 専門用語を並べて煙に巻くことができる
- 質問されても分からないだろうと高をくくれる
- 「信頼してください」の一言で議論を終わらせられる
つまり、曖昧な説明は意図的な戦略である可能性が高いのです。本当に顧客のことを考えるベンダーなら、素人にも分かる言葉で丁寧に説明するはずです。
よくある曖昧な説明パターン
実際にどんな説明が「曖昧」なのか、具体例を見てみましょう:
パターン1:主語が不明確 ❌「システムに影響が出ます」 ⭕「販売管理システムの請求書印刷機能が動作しなくなります」
パターン2:因果関係が不明 ❌「Windows更新でトラブルが発生します」 ⭕「Windows 11ではIEが削除されるため、IE依存の画面が表示できなくなります」
パターン3:範囲が曖昧 ❌「システム全体に影響があります」 ⭕「データベース接続部分とレポート出力機能に影響があります」
パターン4:費用の内訳が不明 ❌「対応費用は150万円です」 ⭕「影響調査30万円、設計40万円、開発60万円、テスト20万円の合計150万円です」
後者のように具体的に説明できるなら、それは「本当に必要な対応」である可能性が高いです。
「可能性」「おそれ」という逃げ道
もう一つの典型的なパターンが、断定を避ける表現です:
- 「影響が出る可能性があります」
- 「トラブルのおそれがあります」
- 「問題が発生するかもしれません」
これらの表現には、「実際には起きないかもしれないが、起きた時に責任を問われたくない」という保身の意図が透けて見えます。
本当に技術的根拠があるなら、「この条件下では確実に発生します」と断定できるはずです。
「他社事例」の一般化という誤魔化し
「別のお客様で問題が発生しましたので、御社も対応が必要です」
一見もっともらしく聞こえますが、重要な情報が抜け落ちています:
- その他社のシステム構成は?
- 使用している技術スタックは?(プログラミング言語、データベースなど)
- 自社のシステムと共通点は?
- 問題の再現性は確認されているか?
これらを確認せずに「他社で起きたから自社も危険」と決めつけるのは、論理的ではありません。
技術的根拠を確認するための10の質問
専門知識がなくても、以下の質問をすることで提案の妥当性を検証できます。
1. 影響を受ける具体的なシステム部分は?
質問例: 「『システム全体』ではなく、具体的にどの機能・画面が影響を受けますか?」
良い回答: 「請求書発行画面、在庫照会画面、月次レポート出力機能の3箇所です」
悪い回答: 「全体的に影響が出る可能性があります」
2. なぜその影響が発生するのか?
質問例: 「Windows更新の何が変わることで、なぜその影響が出るのですか?中学生でも分かるように説明してください」
良い回答: 「Windows 11ではInternet Explorerというブラウザが削除されます。御社システムはこのブラウザ専用に作られているため、画面が表示できなくなります」
悪い回答: 「技術的に複雑で説明が難しいのですが、とにかく対応が必要です」
3. 影響が発生する確率は?
質問例: 「『可能性がある』とのことですが、確率はどのくらいですか?ほぼ確実ですか、それとも10%程度ですか?」
良い回答: 「この構成のシステムでは、過去の事例から見て100%発生します」
悪い回答: 「確率は分かりませんが、リスク回避のため対応をお勧めします」
4. 対応しない場合の具体的な症状は?
質問例: 「もし対応しなかったら、実際にどんな症状が出ますか?システムが完全に止まりますか?」
良い回答: 「請求書印刷時にエラーメッセージが表示され、印刷できなくなります。ただし他の機能は正常に動作します」
悪い回答: 「様々なトラブルが発生する恐れがあります」
5. なぜその金額になるのか?
質問例: 「150万円の内訳を教えてください。何にどれくらいの工数がかかりますか?」
良い回答: 「影響調査20時間、設計30時間、プログラム修正80時間、テスト40時間の計170時間。単価1万円で170万円ですが、御社とは長いお付き合いなので150万円にします」
悪い回答: 「全体的な対応費用として150万円です」
6. 段階的な対応は可能か?
質問例: 「まず影響調査だけを行い、本当に必要な部分だけ改修することはできませんか?」
良い回答: 「可能です。まず調査を30万円で実施し、結果を見て改修範囲を決めましょう」
悪い回答: 「システムは一体なので、全体を一度に対応する必要があります」
7. 代替案はないか?
質問例: 「150万円の改修以外に、もっと低コストな対応方法はありませんか?」
良い回答: 「一時的な回避策として、旧バージョンのブラウザを使う方法もあります。ただし長期的にはお勧めしません」
悪い回答: 「この方法しかありません」
8. 他社でも同じ対応をしているか?
質問例: 「同じシステムを使っている他のお客様も、同じ対応をしていますか?」
良い回答: 「同じシステムを導入している10社のうち、8社は既に対応済みです」
悪い回答: 「他社のことは守秘義務があるのでお答えできません」
9. 保守契約の範囲ではないのか?
質問例: 「Windows更新への対応は、保守契約に含まれないのですか?」
良い回答: 「保守契約は障害対応とバグ修正のみです。OS更新に伴うシステム改修は別途費用となります」
悪い回答: 「これは保守範囲外です」(理由の説明なし)
10. セカンドオピニオンを取ってもよいか?
質問例: 「他のシステム会社にも意見を聞いてから判断したいのですが、システム資料を提供いただけますか?」
良い回答: 「もちろんです。システム構成図と設計書をお渡しします」
悪い回答: 「当社で構築したシステムなので、他社では対応できません」
良いベンダーと悪いベンダーの見分け方
良いベンダーの特徴
✅ 技術用語を使わず、分かりやすく説明できる 「Internet Explorerが使えなくなる」のように、専門家でなくても理解できる言葉を使う
✅ 影響範囲と優先順位を明確にする 「この3箇所は必須、この2箇所は様子見でも可」のように判断材料を提供
✅ 費用の内訳を詳細に説明できる 工数、単価、作業内容を透明化
✅ 代替案を提示してくれる 高額な対応だけでなく、段階的アプローチや低コスト案も検討
✅ 質問を歓迎する 「分からないことがあれば何でも聞いてください」という姿勢
悪いベンダーの特徴
❌ 専門用語で煙に巻く 「APIの互換性が」「レガシーコンポーネントが」と言って、理解を妨げる
❌ 「とにかく対応が必要」としか言わない 具体的な理由や根拠を示さない
❌ 質問すると不機嫌になる 「専門的な話なので説明しても分からないと思います」と突き放す
❌ 他社への相談を嫌がる 「当社しか対応できない」と囲い込む
❌ 不安を煽る 「対応しないと大変なことになります」と脅す
実際の質問で曖昧さを暴いた事例
サービス業G社の場合(従業員45名)
ベンダーからの提案: 「Windows更新により、システムに重大な影響が出ます。全面改修が必要で、費用は200万円です」
G社の質問攻め:
- 「具体的にどの機能が影響を受けますか?」→「システム全体です」
- 「なぜ影響が出るのですか?」→「技術的に複雑で…」
- 「他社でも同じ対応をしていますか?」→「守秘義務が…」
- 「段階的な対応は?」→「一括対応が必要です」
結果: 明確な回答が得られず、セカンドオピニオンを取ることに。別の会社の診断結果は「影響があるのは帳票出力機能のみ。対応費用は40万円」。160万円の過剰請求を回避し、ベンダー変更を決断。
物流業H社の場合(従業員30名)
ベンダーからの提案: 「.NET Frameworkのサポート終了により、システム改修が必要です。費用は100万円です」
H社の質問: 「具体的に何が問題になりますか?」→「セキュリティリスクがあります」 「サポート終了後も動作はしますか?」→「動作はしますが…」 「緊急性は?」→「すぐに対応すべきです」
H社の行動: IT知識のある知人に相談したところ、「確かに長期的には対応すべきだが、今すぐ動かなくなるわけではない。1年後のシステム刷新時に対応すれば十分」とのアドバイス。
結果: 提案を1年保留し、その後クラウドERPへ移行。100万円の無駄遣いを回避しただけでなく、根本的な解決を実現。
まとめ:「分からないから」で終わらせない
技術的な知識がないからといって、曖昧な説明を受け入れる必要はありません。優れたベンダーは、専門家でなくても理解できるように説明する能力を持っています。
今日から実践できること:
- 次回提案を受けた際、この記事の10の質問を使って確認する
- 曖昧な回答しか得られない場合は、判断を保留する
- 必ずセカンドオピニオンを取る
- 説明能力が低いベンダーとの関係を見直す
「よく分からないけど、専門家が言うなら…」という思考停止が、年間数百万円の無駄遣いを生んでいます。
適切な質問をする。明確な回答を求める。それだけで、あなたの会社のIT投資は劇的に最適化されます。
もし現在のベンダーの説明に納得できていないなら、まずはセカンドオピニオンから始めてみませんか?
お問い合わせは今すぐ! 「この提案は本当に必要?」専門用語を使わず、分かりやすい言葉で説明します。ベンダーの提案を客観的に評価する、セカンドオピニオンサービスをご利用ください。