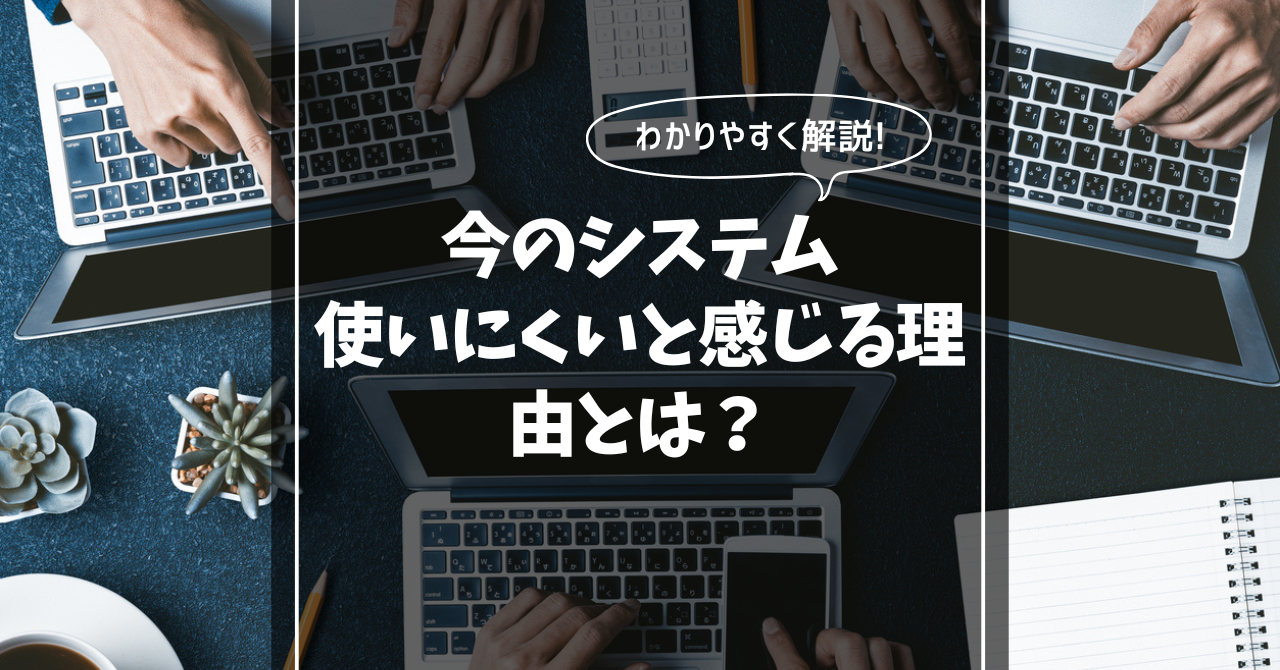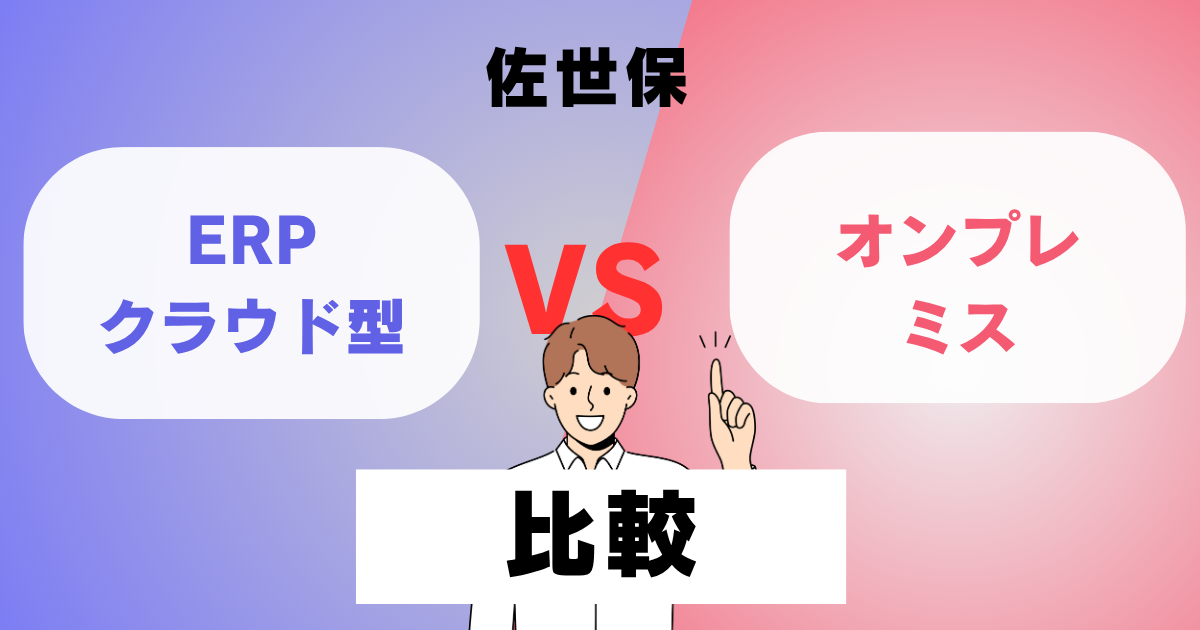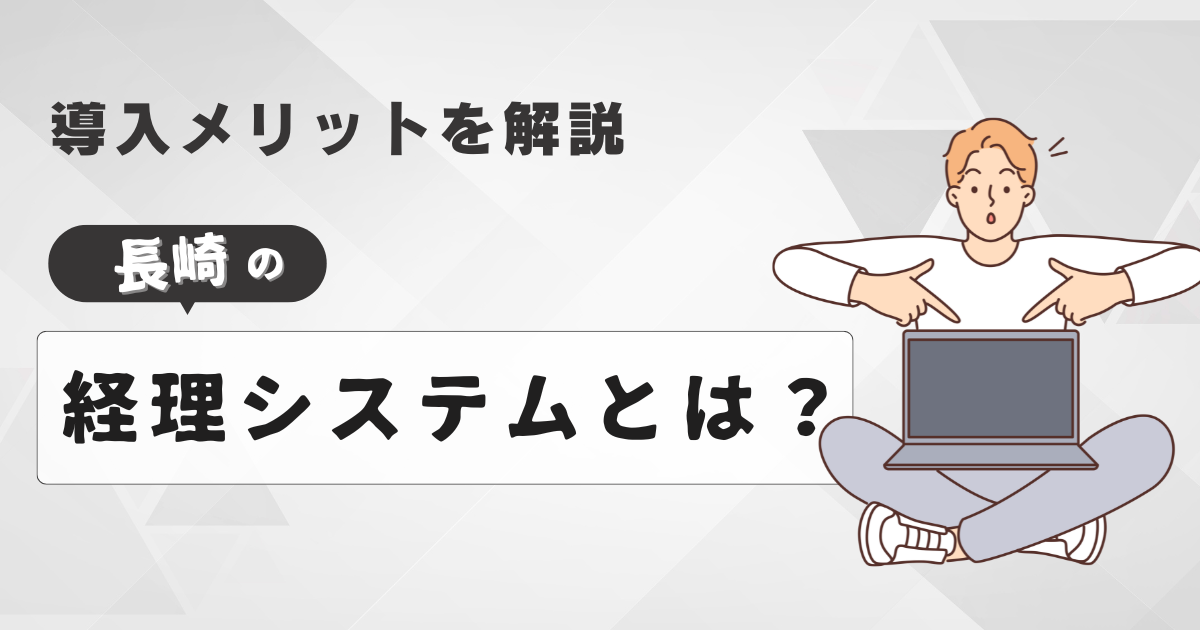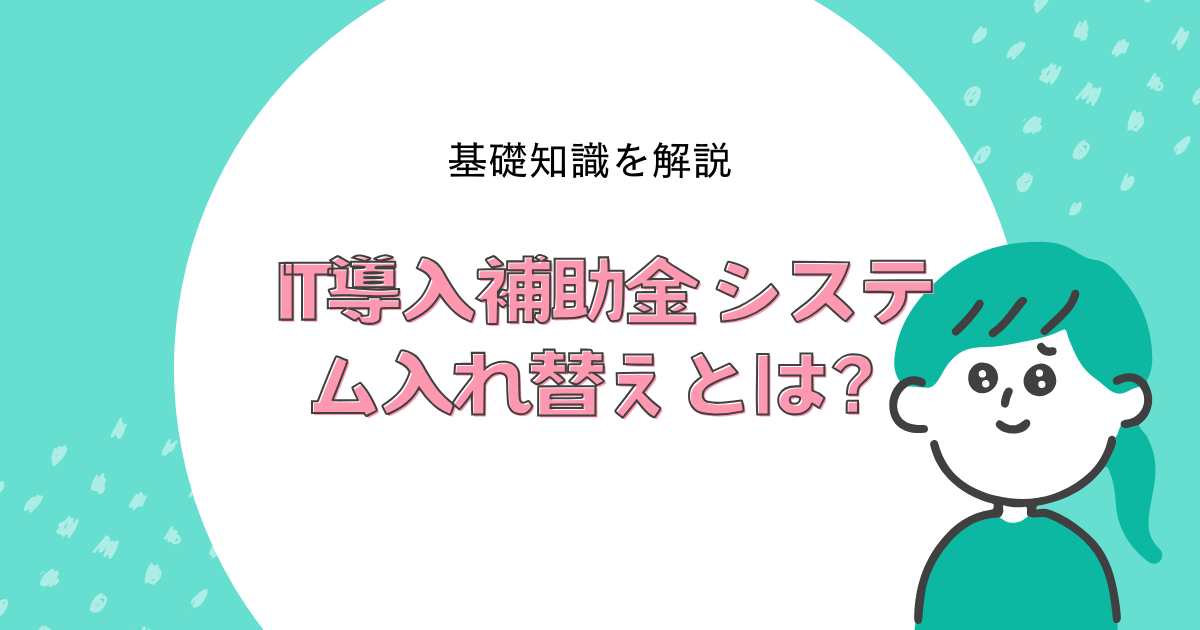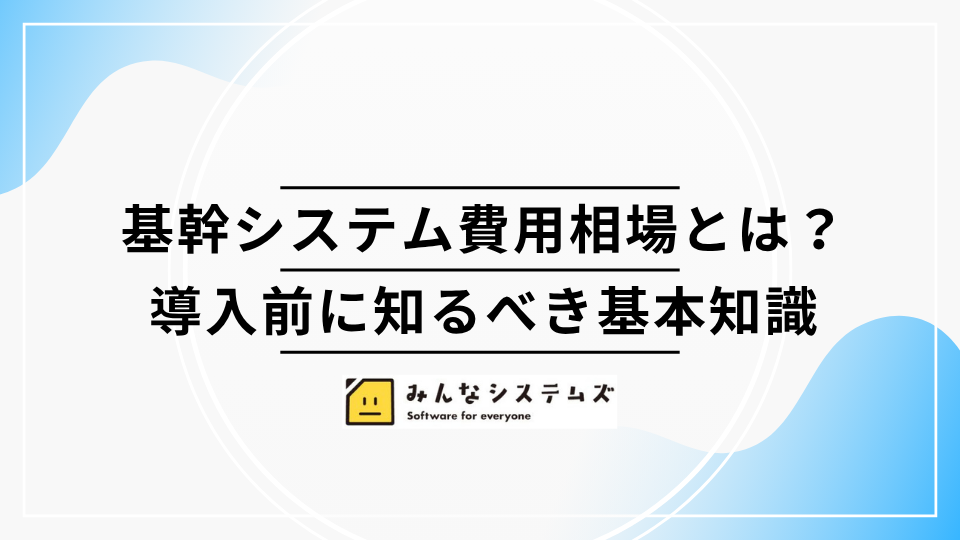みなさんこんにちは株式会社みんなシステムズの営業の大石です。日々お客様と接する中で「今使っているシステムが使いにくくて困っている」というお声を本当によく耳にします。
実は先日も長崎県佐世保市のお客様から同様のご相談をいただき、基幹システムのリプレイスをお手伝いさせていただきました。
その経験も踏まえて、今回はシステムが使いにくいと感じる原因について詳しく解説していきたいと思います。
システムが使いにくいと感じる主な原因
操作が複雑で分かりにくい
今のシステム使いにくいと感じる最も大きな要因は、操作の複雑さです。
多くのシステムでは、同じ目的を達成するために複数の手順が必要で、ユーザーが迷いやすい構造になっています。特に、メニューが深い階層になっていたり、似たような機能が複数の場所に散らばっていると、ユーザーの混乱を招きます。
佐世保市のお客様の事例では、受注データを入力するのに7つの画面を行き来する必要があり、1件の入力に平均15分もかかっていました。必要な情報が複数の画面に分散していて、入力の都度画面を切り替えなければならず、入力ミスも頻発していたのです。さらに、同じような項目を何度も入力する必要があるなど、非効率的な作業フローが日常化していました。
レスポンスが遅い・動作が重い
システムの処理速度が遅いことも使いにくさの大きな原因です。画面の切り替えに時間がかかったり、データの読み込みが遅いと、ユーザーのストレスが蓄積されます。特に繁忙期や月末など、アクセスが集中する時期には、システムが固まってしまうこともあります。佐世保のお客様も、在庫確認をするだけで画面が表示されるまで30秒以上待たされることがあり、電話対応中のお客様をお待たせしてしまうという問題を抱えていました。
ユーザーインターフェースの問題点
直感的でないデザイン
優れたシステムは直感的な操作が可能ですが、使いにくいシステムでは、ボタンの配置や色使い、アイコンの意味が分かりにくく設計されています。例えば、重要なボタンが目立たない場所にあったり、削除ボタンと確定ボタンが隣り合って配置されていたりすると、操作ミスを誘発します。また、エラーメッセージが専門用語だらけで、何が問題なのか理解できないケースも少なくありません。
必要な機能が見つからない
頻繁に使用する機能が見つけにくい場所にあったり、検索機能が不十分だと、ユーザーは目的の操作を完了するまでに時間がかかってしまいます。佐世保市の事例では、営業担当者が外出先から在庫確認をしようとしても、複雑なメニュー階層を辿らなければならず、お客様の前で長時間システムと格闘することになっていました。これでは営業活動に集中できず、商談の機会損失にもつながっていたのです。
システム設計上の課題
ユーザーのニーズとのミスマッチ
システム開発時に実際の利用者の声が十分に反映されていない場合、現場のニーズと機能が合わない問題が発生します。開発側が想定した使い方と、実際の業務フローが異なることはよくあることです。例えば、経理部門向けに設計されたシステムを営業部門でも使用する場合、営業特有の業務には対応できていないことがあります。現場の声を聞かずに導入されたシステムは、結果として誰にとっても使いにくいものになってしまいます。
古い技術による制約
レガシーシステムでは、新しい技術やデザイン手法を取り入れることが困難で、現代のユーザビリティ基準に対応できていません。10年以上前に開発されたシステムでは、スマートフォンやタブレットでの利用が想定されておらず、外出先からのアクセスが困難だったり、画面が小さいデバイスでは操作できなかったりします。また、古いブラウザにしか対応していないため、セキュリティ面でも不安が残ることがあります。
使いにくさが業務に与える影響
作業効率の低下
システムの使いにくさは直接的に作業効率に影響します。調査によると、使いにくいシステムは作業時間を平均20-30%増加させるとされています。佐世保市のお客様の場合、リプレイス前は1日の業務時間の約3分の1をシステム操作に費やしていました。これは年間で考えると膨大な時間のロスであり、人件費に換算すると相当な金額になります。単純作業に時間を取られることで、本来注力すべき顧客対応や企画立案などの付加価値の高い業務に時間を割けなくなっていました。
ストレスとモチベーション低下
毎日使用するシステムが使いにくいと、従業員のストレスが蓄積し、業務に対するモチベーション低下につながります。特に新入社員にとっては、システムの操作を覚えることが大きな負担となり、本来の業務習得が遅れる原因にもなります。佐世保市の事例でも、システムの使いにくさが原因で離職を考える社員が出てきており、人材確保の観点からも早急な対応が必要でした。
システム改善のポイント
使いやすいシステムにするためには、ユーザー中心設計の採用が重要です。定期的なユーザビリティテストの実施、シンプルなナビゲーション設計、レスポンス速度の改善が効果的です。
佐世保市でのリプレイス事例では、まず現場の声を徹底的にヒアリングし、実際の業務フローに沿ったシステム設計を行いました。その結果、UIが大幅に改善され、受注入力にかかる時間が15分から3分に短縮されました。画面遷移を最小限に抑え、一画面で必要な情報をすべて確認・入力できるようにしたことで、作業効率が飛躍的に向上したのです。
さらに、営業担当者向けにはモバイル対応を強化し、スマートフォンやタブレットから簡単に在庫確認ができるようになりました。外出先でもリアルタイムで在庫状況を把握できるようになったことで、お客様への即答が可能になり、受注率が約20%向上しました。営業担当者からは「お客様の前で待たせることなく、スムーズに商談が進められるようになった」「移動時間を有効活用できるようになった」といった喜びの声をいただいています。
まとめ
今のシステム使いにくいと感じる原因は、操作の複雑さ、UI設計の問題、技術的制約など多岐にわたります。これらの問題を解決するには、ユーザーの声を聞き、継続的な改善を行うことが不可欠です。佐世保市での成功事例が示すように、適切なシステムリプレイスは単なる効率化だけでなく、従業員の満足度向上、売上アップ、そして企業の競争力強化につながります。システムの使いにくさでお悩みの企業様は、ぜひ一度現状のシステムを見直してみることをおすすめします。私たち株式会社みんなシステムズは、お客様の業務に最適なシステム構築をお手伝いさせていただきます。
```