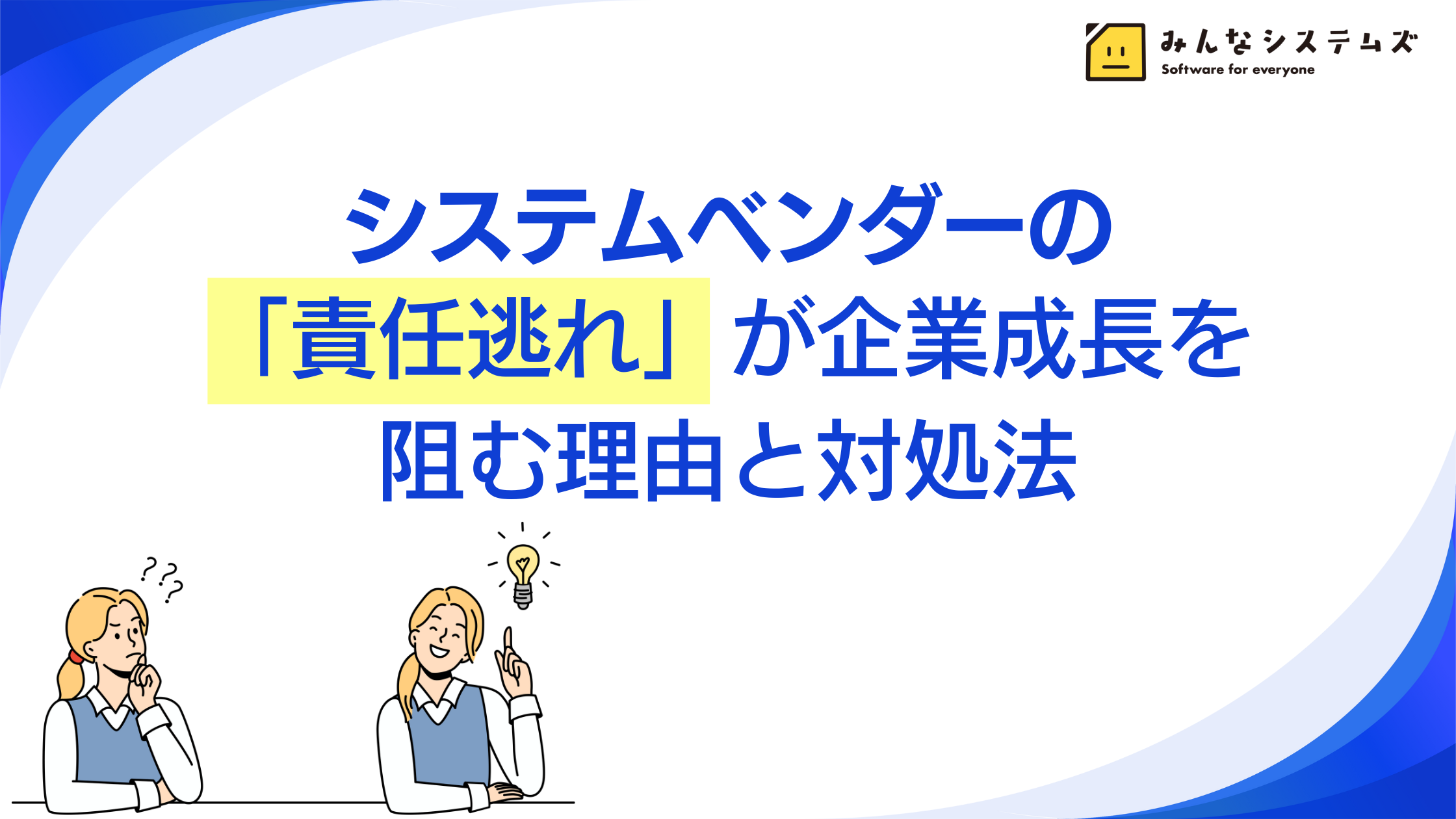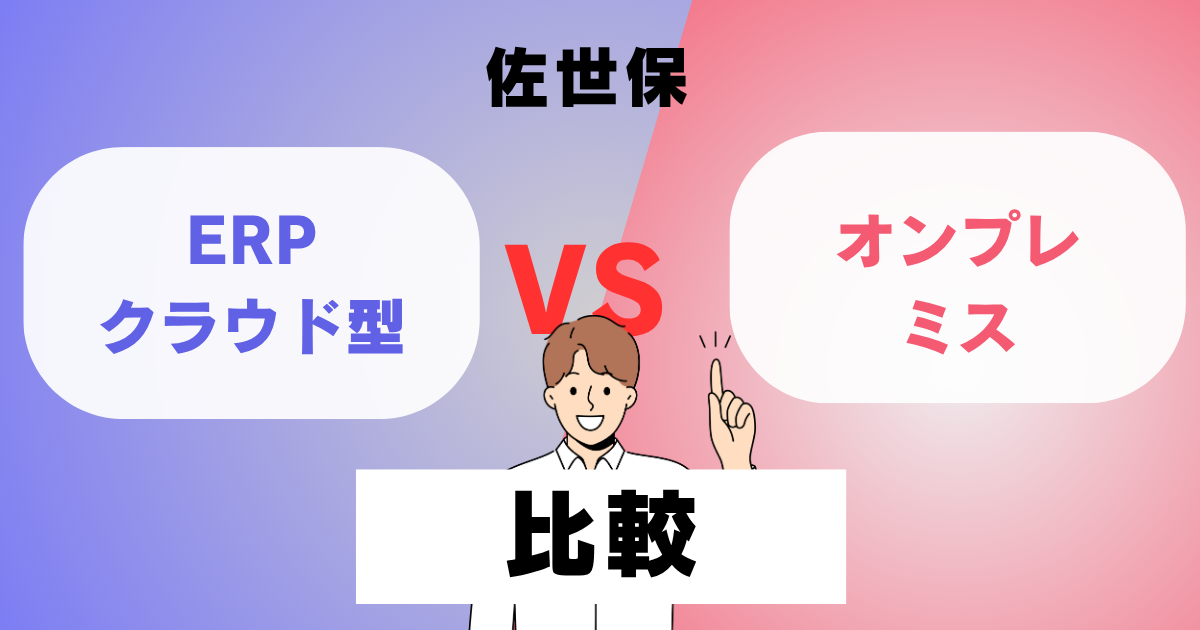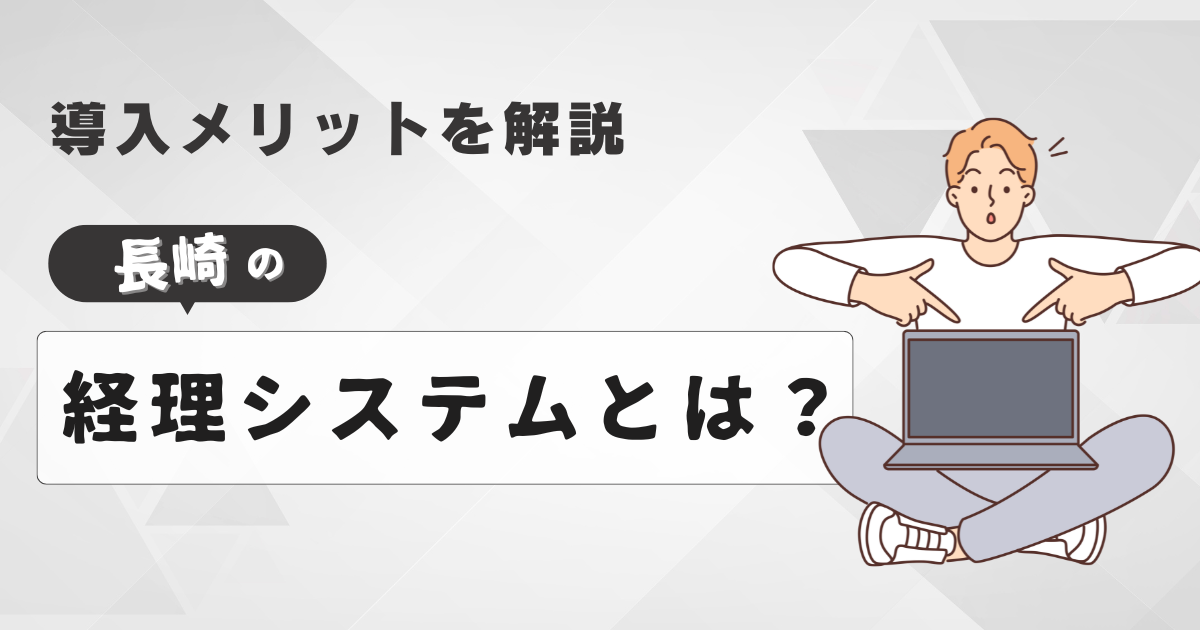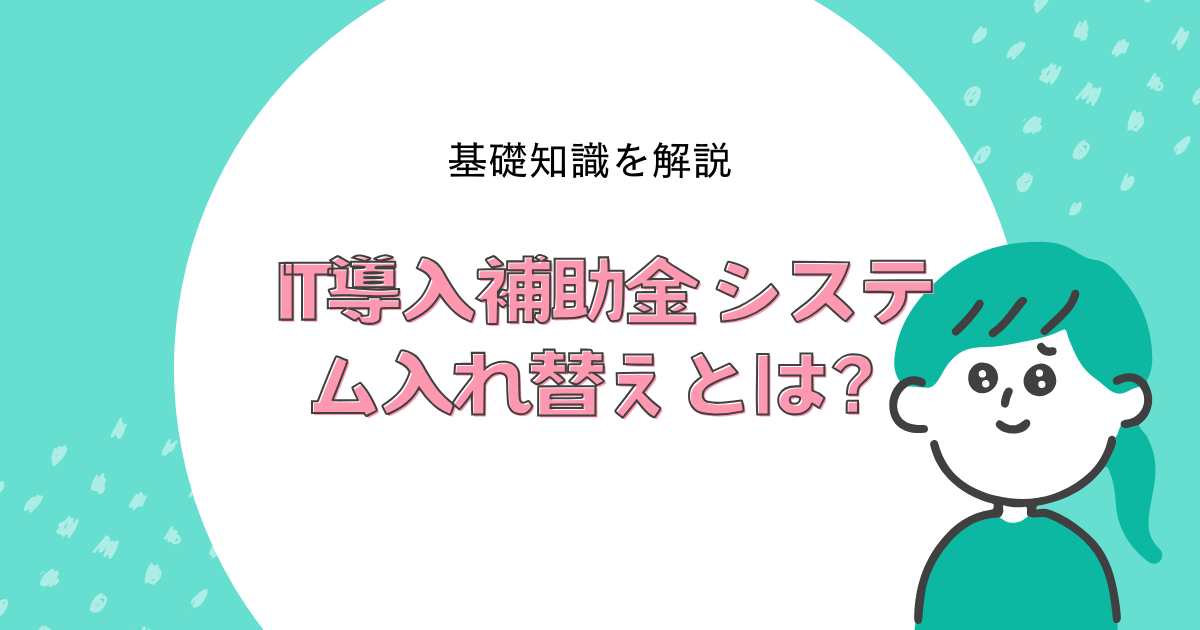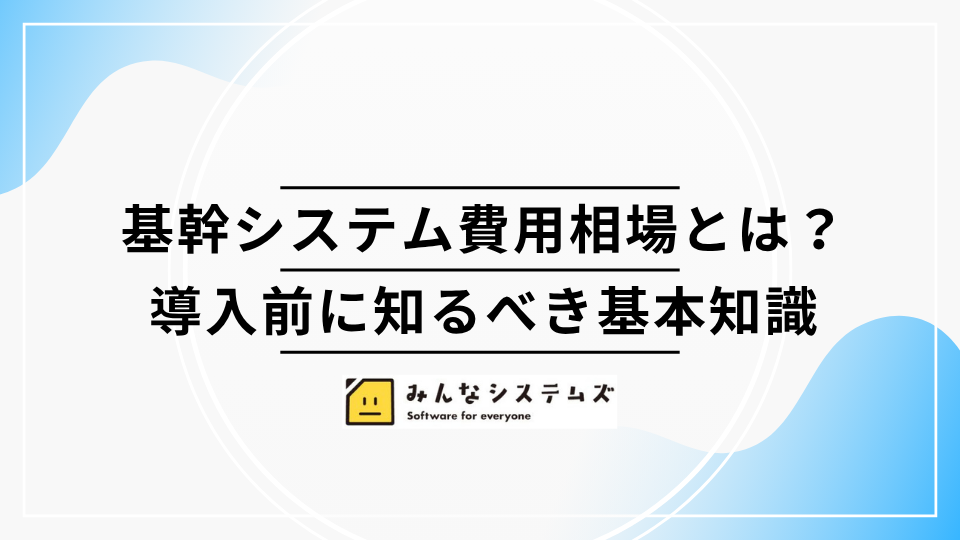「それは御社の操作ミスです」──その一言に隠された問題
システムに不具合が発生し、業務が止まってしまった。慌てて保守サポートに連絡すると、返ってくるのは決まってこんな言葉です。
「それは御社側の操作ミスが原因ですね」
詳しい調査もなく、ログ(システムの操作記録)の確認もせずに、顧客側の責任として片付けられる──。こうした「責任逃れの体質」を持つベンダー(システム開発・保守会社)との付き合いに、多くの中小企業が苦しんでいます。
実はこの問題、単なる対応の悪さではありません。企業のDX推進や業務効率化を根本から阻害する、深刻な構造的課題なのです。
なぜ「責任逃れ」が起きるのか──3つの背景
1. 保守契約の曖昧さ
多くの中小企業では、システムの保守契約において「どこまでがベンダーの責任範囲か」が明確に定義されていません。この曖昧さを利用し、不具合が発生すると「契約範囲外」「操作ミス」として処理されてしまうケースが頻発しています。
2. 技術力・調査力の不足
本来、システムの不具合調査には、ログ解析やデータベースの状態確認など、専門的な技術と時間が必要です。しかし技術力が不足しているベンダーは、詳細な原因究明ができず、安易に「操作ミス」という結論に逃げる傾向があります。
3. 「顧客は素人」という意識
「どうせ顧客はシステムのことが分からない」──そんな意識が根底にあるベンダーは、説明責任を果たそうとしません。専門用語を並べて煙に巻いたり、証拠を示さずに断定したりする対応は、この意識の表れです。
責任逃れベンダーがもたらす3つの深刻な損失
経済的損失
不具合の本質的な原因が解決されないため、同じトラブルが繰り返し発生します。その度に業務が停止し、復旧対応に時間を取られ、本来の業務に集中できません。さらに、原因が曖昧なまま追加費用を請求されるケースもあります。
機会損失
「またシステムが止まるかもしれない」という不安から、新しい機能の活用や業務プロセスの改善に踏み出せなくなります。せっかく導入した販売管理システムやERPが、本来の能力の半分も使われていない状況が生まれます。
人材の疲弊
担当者は常に「システムが止まったらどうしよう」という不安を抱え、トラブル対応に追われます。本来注力すべき業務改善やデータ活用といった前向きな仕事ができず、モチベーション低下や離職につながるケースも珍しくありません。
「誠実なベンダー」を見極める5つのポイント
1. 調査プロセスの透明性
不具合発生時、「まずログを確認させてください」「データの状態を調査します」と、具体的な調査手順を説明できるベンダーは信頼できます。一方で、即座に「操作ミスです」と断定するベンダーは要注意です。
2. エビデンス(証拠)の提示
原因究明の結果を、ログのスクリーンショットやデータの比較表など、具体的な証拠とともに説明できることが重要です。「こうなっているから、こう判断しました」という説明ができるかどうかが分かれ目です。
3. 改善提案の有無
たとえ操作ミスが原因だったとしても、「なぜそのミスが起きたのか」「再発防止のために何ができるか」を一緒に考えてくれるベンダーは、真のパートナーです。ユーザーインターフェースの改善提案や操作マニュアルの見直しなど、建設的な対応ができるかどうかを見極めましょう。
4. 契約内容の明確化
保守契約で「どこまでが無償対応か」「どんな場合に追加費用が発生するか」を明確に文書化しているベンダーは、責任範囲を曖昧にしません。
5. 過去の実績と評判
同業種・同規模の企業での導入実績や、既存顧客の生の声を確認することが重要です。特に「トラブル時の対応」について、具体的なエピソードを聞いてみることをお勧めします。
実際にあった事例:製造業A社のケース
従業員50名の製造業A社では、15年前に導入した販売管理システムで頻繁にエラーが発生していました。保守ベンダーに連絡すると「操作が間違っている」「データの入力順序が悪い」と言われ続け、根本的な解決には至りませんでした。
業を煮やしたA社は、別のシステム会社にセカンドオピニオンを依頼。詳細な調査の結果、システムのプログラムに古いバグが残っていたこと、そして特定の条件下でデータベースが不整合を起こす設計上の欠陥があることが判明しました。
新しいベンダーは、これらの問題を詳細な報告書にまとめ、システム刷新の提案を実施。結果として、A社は最新のクラウドERPへ移行し、トラブル対応の時間が月40時間削減され、その時間を売上拡大のための営業活動に充てられるようになりました。
「あの5年間は何だったのか」──A社の社長はこう振り返ります。「もっと早くベンダーを変える決断をすべきだった」
まとめ:システムは「任せる」ではなく「選ぶ」時代へ
システムベンダーの責任逃れの体質は、単なるサポート品質の問題ではありません。企業の成長と従業員の働きがいを直接的に阻害する、経営課題です。
中小企業にとって、基幹システムは今や事業の生命線です。だからこそ、「安いから」「昔から付き合いがあるから」という理由でベンダーを選び続けるのではなく、誠実に向き合ってくれるパートナーを選ぶことが重要です。
もし今のベンダーとの関係に少しでも疑問を感じているなら、それは見直しのサインかもしれません。セカンドオピニオンを受けてみる、他社の提案を聞いてみるだけでも、新しい視点が得られるはずです。
システムは「使いこなす」ものから「成長を支える」ものへ。そのためには、責任を持って伴走してくれるベンダーとの関係構築が、何よりも大切なのです。