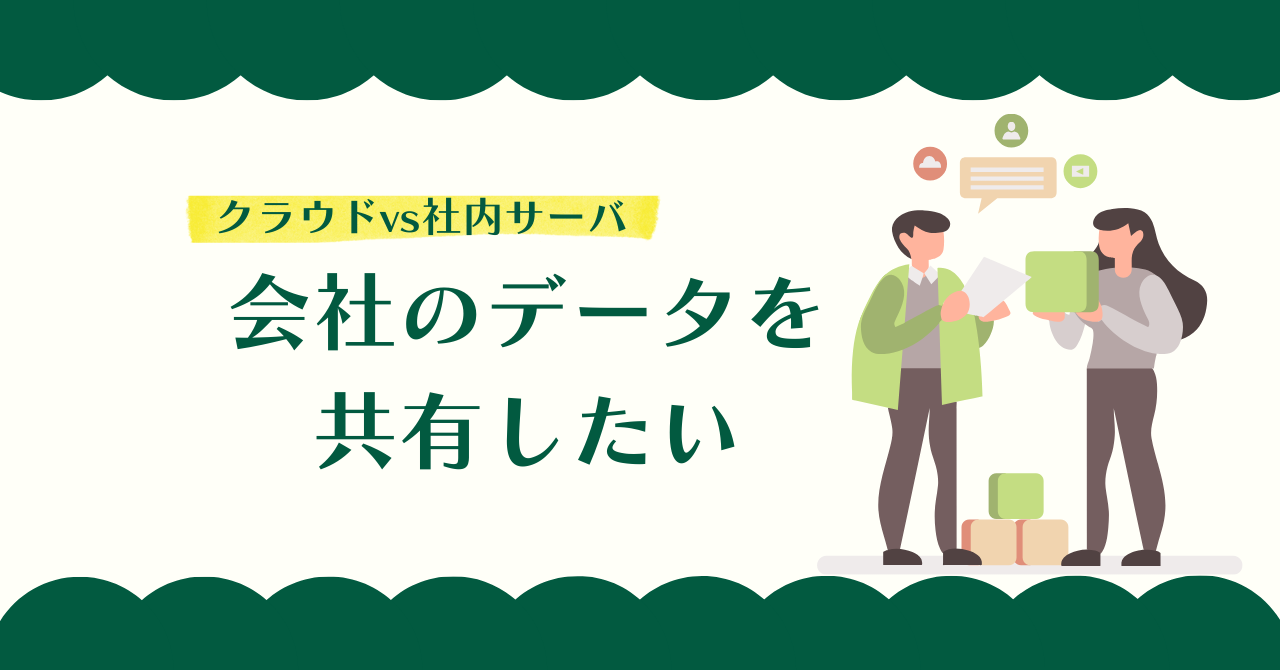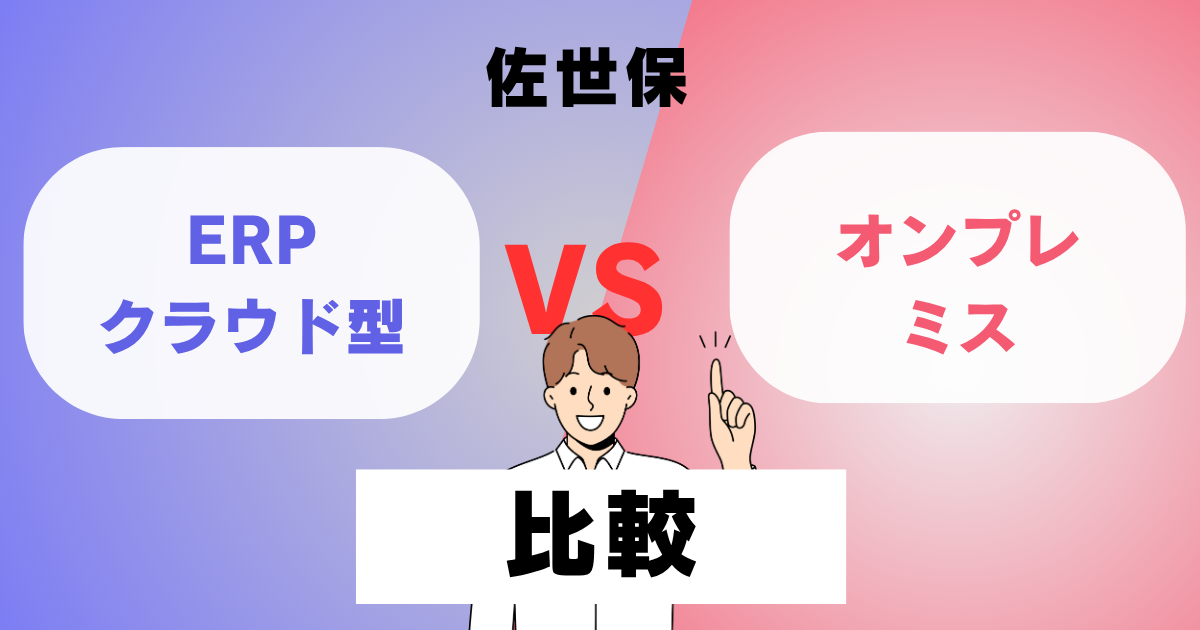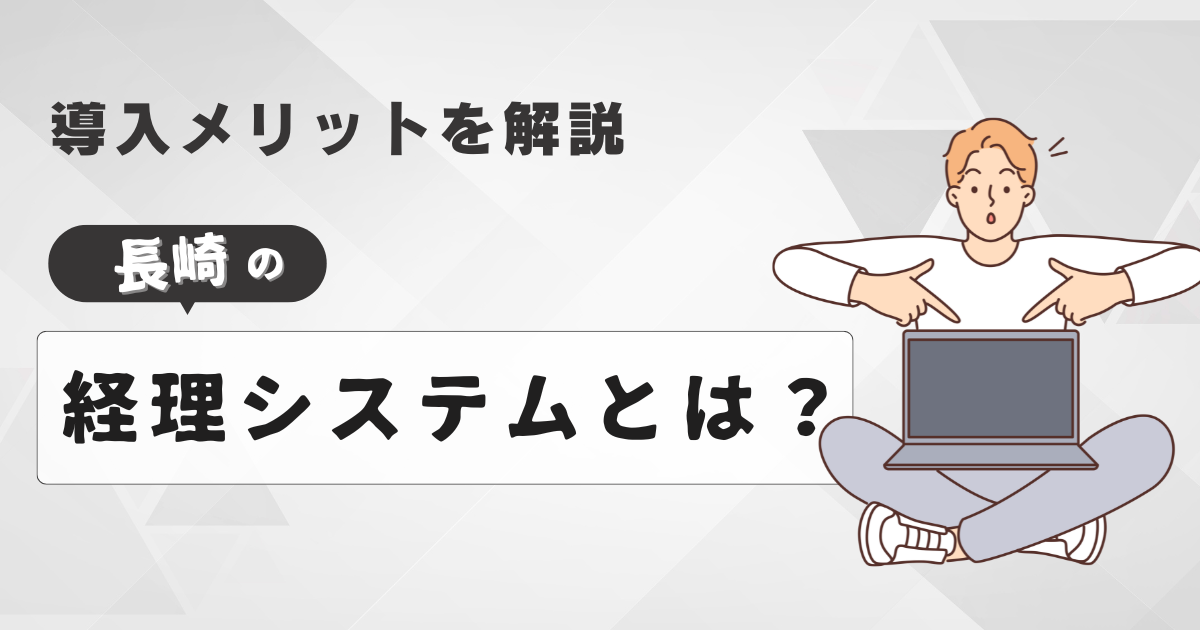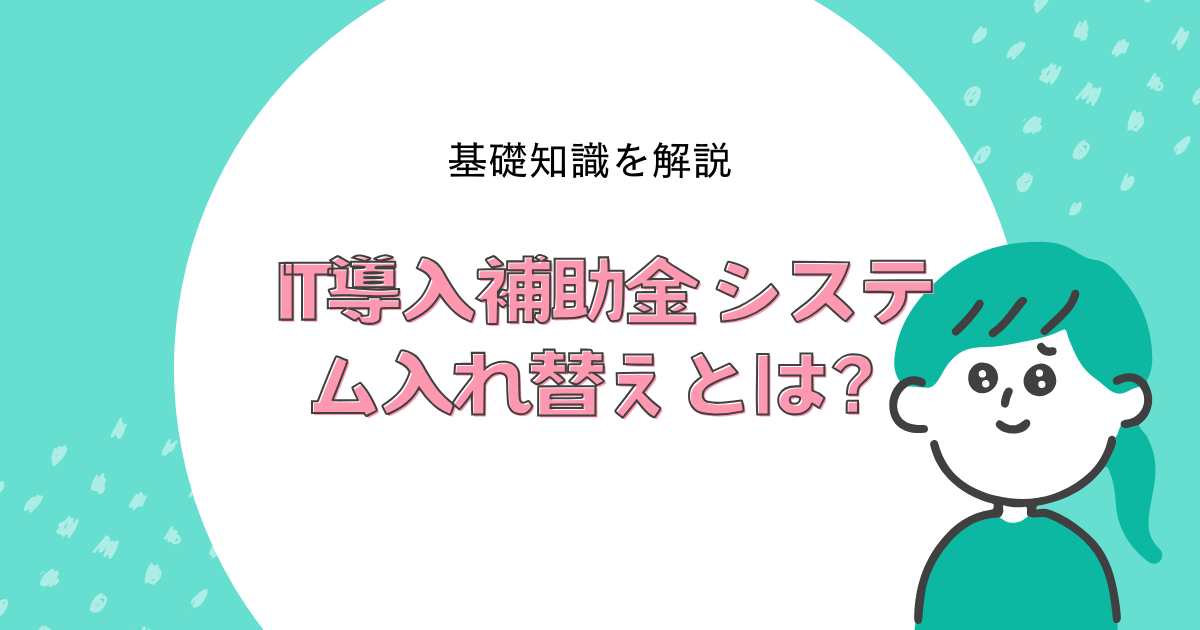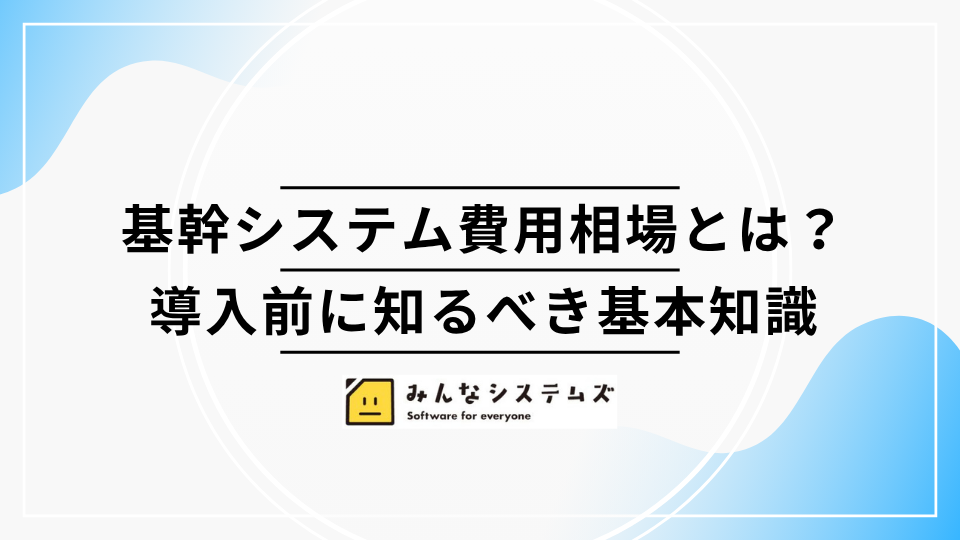みなさんこんにちは、株式会社みんなシステムズの営業の岩永です。
最近、お客様から「社内のデータ共有をもっと効率化したい」というご相談をよくいただきます。特にリモートワークが当たり前になった今、どこからでも安全にデータにアクセスできる環境づくりは多くの企業様の課題になっているようですね。今日は、クラウドと社内サーバ、どちらがいいのか迷っている方に向けて、実際の導入事例も交えながらお話しさせていただきます。
会社のデータ共有が重要な理由
現代のビジネスでは、会社のデータを共有したいというニーズが急速に高まっています。リモートワークの普及により、社員が場所を問わずファイルにアクセスできる環境が必要不可欠となりました。効率的なデータ共有により、プロジェクトの進行速度向上や意思決定の迅速化が実現できます。
実際に、つい先日も「営業が外出先でお客様に資料を見せたいのに、会社に戻らないとファイルが取れない」というお悩みを伺いました。こうした状況では、せっかくの商談チャンスを逃してしまう可能性もありますよね。データ共有の仕組みを整えることは、もはや業務効率化のオプションではなく、競争力を維持するための必須条件になっています。
また、複数の部署で同じプロジェクトに取り組む際、最新版のファイルがどれなのかわからなくなった経験はありませんか?「資料v1」「資料v2」「資料_最終版」「資料_最終版_確定」なんてファイルが乱立している光景、よく見かけますよね(笑)。適切なデータ共有環境があれば、こうした混乱も防げるんです。
クラウドストレージとは?
クラウドストレージは、インターネット経由でデータを保存・共有できるサービスです。代表的なサービスにGoogle Drive、Microsoft OneDrive、Dropboxがあります。
「雲の上にデータを保存する」なんて表現されることもありますが、実際には世界各地にあるデータセンターにファイルが保存されています。私たちユーザーは、インターネット経由でそのデータにアクセスするという仕組みですね。
クラウドのメリット
- 初期費用が安い:サーバー購入が不要
- どこからでもアクセス可能:インターネット環境があれば利用可能
- 自動バックアップ機能:データ消失リスクが低い
- スケーラビリティ:容量を柔軟に変更可能
クラウドの最大の魅力は、なんといってもその手軽さです。契約した当日から使い始められますし、スマートフォンからでもアクセスできる便利さは格別です。私も移動中によく活用していますが、電車の中で急ぎの資料を確認できるのは本当に助かります。
また、自動的にバックアップが取られるので、「パソコンが壊れてデータが全部消えた!」なんて悲劇も防げます。実際に、お客様の中にも「パソコンを盗まれたけど、クラウドにデータがあったので被害は最小限だった」という方がいらっしゃいました。
クラウドのデメリット
- 月額料金が継続的に発生
- インターネット接続が必須
- セキュリティ面で第三者への依存
一方で、継続的な費用負担は避けられません。最初は「月額数千円なら安い」と感じても、年単位、数年単位で考えると結構な金額になることもあります。また、インターネット接続が不安定な場所では使いにくいという問題もありますね。
社内サーバとは?
社内サーバは、自社内に設置する物理的なサーバーでデータを管理する方法です。完全に自社でコントロールできる環境を構築できます。
「サーバー」と聞くと大げさに聞こえるかもしれませんが、最近は小型で手頃なものも多く出ています。NAS(Network Attached Storage)なんて呼ばれる機器は、外付けハードディスクの進化版みたいなもので、思っているより身近な存在なんですよ。
社内サーバのメリット
- 完全な自社管理:セキュリティポリシーを独自に設定
- 高速アクセス:社内ネットワーク経由で高速通信
- カスタマイズ性:業務に特化したシステム構築が可能
社内サーバの一番のメリットは、「自分たちの思い通りにできる」ことです。アクセス権限の設定も、データの保存期間も、バックアップのタイミングも、すべて自社の判断で決められます。
佐世保市での成功事例
実際に、長崎県佐世保市のお客様で、社内サーバとクラウドのハイブリッド型システム導入を支援させていただいた事例があります。このお客様は製造業で、図面データなど機密性の高い情報は社内サーバで管理し、営業資料や一般的な文書はクラウドで共有するという使い分けを行いました。
基幹システムのリプレイスと同時に実施したのですが、以前は営業担当者が在庫情報を確認するために、いちいち工場に電話をかけて確認していました。新しいシステムでは、営業用タブレットから直接在庫データベースにアクセスできるようになり、お客様との商談中にリアルタイムで在庫状況と納期をお答えできるようになったんです。
UIも大幅に改善し、従来は複雑な操作で10分以上かかっていたデータ入力が、わずか2〜3分で完了するようになりました。結果として、営業チーム全体の生産性が約40%向上したという結果も出ています。
社内サーバのデメリット
- 高い初期投資:サーバー機器やソフトウェア購入費用
- 専門知識が必要:IT管理者の配置が必須
- 保守・運用コスト:定期的なメンテナンスが必要
社内サーバの大きな課題は、やはり初期費用と運用の複雑さです。機器を購入してセットアップするだけでも相当な手間がかかりますし、何か問題が起きた時に対応できる人がいないと大変なことになってしまいます。
以前、あるお客様から「サーバーが動かなくなって、IT担当者が休暇中で誰も対応できない」という緊急連絡をいただいたことがありました。幸い私たちがサポートできましたが、そうした体制がないと業務が完全にストップしてしまう可能性もあります。
コスト面での比較
初期費用では社内サーバが100万円以上かかる一方、クラウドは月額数千円から開始可能です。ただし、長期運用では社内サーバの方が総コストを抑えられる場合があります。従業員50人規模の企業では、3年目以降に社内サーバの方がコスト効率が良くなる傾向があります。
具体的な数字でお話しすると、従業員30人の企業でクラウドサービスを利用した場合、月額約5万円程度かかることが多いです。年間で60万円、3年で180万円になります。一方、社内サーバは初期費用150万円程度かかりますが、3年目以降は保守費用のみで運用できるため、長期的には社内サーバの方が経済的になることがあります。
ただし、これは単純な機器費用だけの話です。社内サーバの場合は、電気代、IT担当者の人件費、トラブル対応費用なども考慮する必要があります。総合的に判断すると、どちらが得かは企業の状況によって大きく変わるんですね。
セキュリティ面での比較
クラウドサービスは企業レベルのセキュリティを提供しますが、データの物理的な保存場所は把握できません。社内サーバは完全な自社管理により、厳格なセキュリティポリシーを適用できますが、専門知識がないと脆弱性が生じるリスクがあります。
セキュリティについては、実は「どちらが安全」とは一概に言えません。大手クラウドサービスは、個人や中小企業では到底用意できないレベルの高度なセキュリティ対策を講じています。専門のセキュリティチームが24時間監視していますし、最新の脅威に対する対策も迅速に実施されます。
一方、社内サーバは「自分たちで守る」必要があります。適切に管理されていれば非常に安全ですが、設定ミスやアップデート漏れがあると、かえって危険な状態になってしまうこともあります。
佐世保市のお客様の場合も、当初は「社内サーバの方が安全」と考えられていましたが、実際に運用を始めてみると、定期的なセキュリティアップデートやウイルス対策の管理が想像以上に大変だったそうです。そこで、機密データは社内サーバ、一般的なデータはクラウドという使い分けを採用されました。
運用・保守の違い
クラウドサービスはベンダーが運用・保守を担当するため、社内のIT負荷を軽減できます。社内サーバは自社での運用・保守が必要で、システム管理者の確保やトラブル対応体制の構築が必要です。
この差は、想像以上に大きいものです。クラウドサービスなら、システムのアップデートも自動で行われますし、障害が発生してもサービス提供会社が対応してくれます。利用者は「使うだけ」でいいんです。
社内サーバの場合は、日々の監視から定期メンテナンス、トラブル対応まで、すべて自社で行う必要があります。「土日にサーバーがダウンして、月曜日の朝から業務が止まった」なんてことになったら大変ですよね。
ただし、社内サーバにもメリットがあります。何か問題が起きても、原因や対応策を自社で把握できるため、迅速な解決が可能です。クラウドサービスで障害が発生した場合、復旧まで待つしかないという状況もあります。
アクセス性と利便性の比較
現代の働き方を考えると、アクセス性は非常に重要な要素です。クラウドサービスは、インターネットさえあればどこからでもアクセスできるため、リモートワークや出張先での作業に最適です。スマートフォンアプリも充実しているので、移動中でも簡単にファイルを確認できます。
佐世保市のお客様でも、営業担当者が「外出先でお客様に急に資料を求められても、すぐにタブレットで表示できるようになった」と喜んでいらっしゃいました。以前は「会社に戻って資料を取ってから」という対応でしたが、今では商談の場でリアルタイムに情報を提供できるため、成約率も向上したそうです。
一方、社内サーバは社内ネットワーク経由でのアクセスが基本となるため、外部からのアクセスには VPN などの仕組みが必要になります。設定や運用は複雑になりますが、社内での利用に限定すれば非常に高速で快適なアクセスが可能です。
どちらを選ぶべき?選択のポイント
クラウドがおすすめ:
- 従業員数50人以下の中小企業
- IT管理者がいない
- 初期費用を抑えたい
- リモートワークを積極的に活用したい
- スピーディーな導入を希望する
社内サーバがおすすめ:
- 機密性の高いデータを扱う
- IT管理者が在籍している
- 長期的なコスト削減を重視
- 既存システムとの連携が重要
- 独自のカスタマイズが必要
選択に迷った時は、まず「何を一番重視するか」を明確にすることが大切です。コストなのか、セキュリティなのか、利便性なのか。優先順位を決めることで、自然と答えが見えてくることが多いんです。
また、「どちらか一つを選ばなければならない」というわけでもありません。佐世保市のお客様のように、用途に応じて使い分けるハイブリッド型の運用も、とても効果的な選択肢です。
おすすめのツール紹介
クラウド系:Microsoft 365(月額540円/ユーザー)、Google Workspace(月額680円/ユーザー)
社内サーバ系:Windows Server、NAS(Network Attached Storage)
クラウドサービスを選ぶ際は、既に使っているソフトウェアとの連携を考慮することが重要です。Excelをよく使う企業ならMicrosoft 365、Gmailを使っているならGoogle Workspaceが使いやすいでしょう。
社内サーバを検討される場合は、まずは小規模なNAS から始めてみることをおすすめします。数十万円程度で導入でき、運用の経験を積むことができます。その後、必要に応じて本格的なサーバーに移行するという段階的なアプローチも有効です。
導入時の注意点とベストプラクティス
どちらを選択する場合でも、導入時に気をつけていただきたいポイントがあります。
まず、段階的な移行を心がけることです。いきなりすべてのデータを新しい環境に移そうとすると、混乱が生じやすくなります。重要度の低いデータから順次移行し、問題がないことを確認してから本格運用に移るのがおすすめです。
次に、スタッフの教育も重要です。どんなに良いシステムを導入しても、使う人が操作方法を理解していなければ効果は半減してしまいます。佐世保市のお客様でも、新システム導入時には全社員向けの研修を実施し、操作マニュアルも作成されました。
また、バックアップ戦略についても事前に検討しておきましょう。クラウドサービスでも、誤ってファイルを削除してしまうリスクはあります。社内サーバの場合は、さらに慎重なバックアップ計画が必要です。
まとめ
会社のデータを共有したい企業は、自社の規模、予算、セキュリティ要件を総合的に判断して選択することが重要です。まずは小規模でクラウドから始めて、必要に応じて社内サーバへの移行を検討するのも有効な戦略です。
私がお客様にいつもお伝えしているのは、「完璧な解決策を最初から求めすぎない」ということです。まずは現在の課題を解決できる方法を選択し、運用しながら改善していくのが現実的なアプローチだと思います。
佐世保市のお客様も、最初は「どちらが正解かわからない」とおっしゃっていましたが、段階的に導入を進めることで、最適な形を見つけることができました。UIの改善により作業効率が大幅に向上し、営業チームの生産性向上にもつながっています。
データ共有の仕組みづくりは、一度構築すれば長期間にわたって企業の生産性向上に貢献します。最初の選択で悩まれるのは当然ですが、まずは第一歩を踏み出すことが大切です。
何かご不明な点や具体的なご相談がございましたら、いつでもお気軽にお声がけください。みなさんの会社に最適な解決策を一緒に見つけていきましょう!